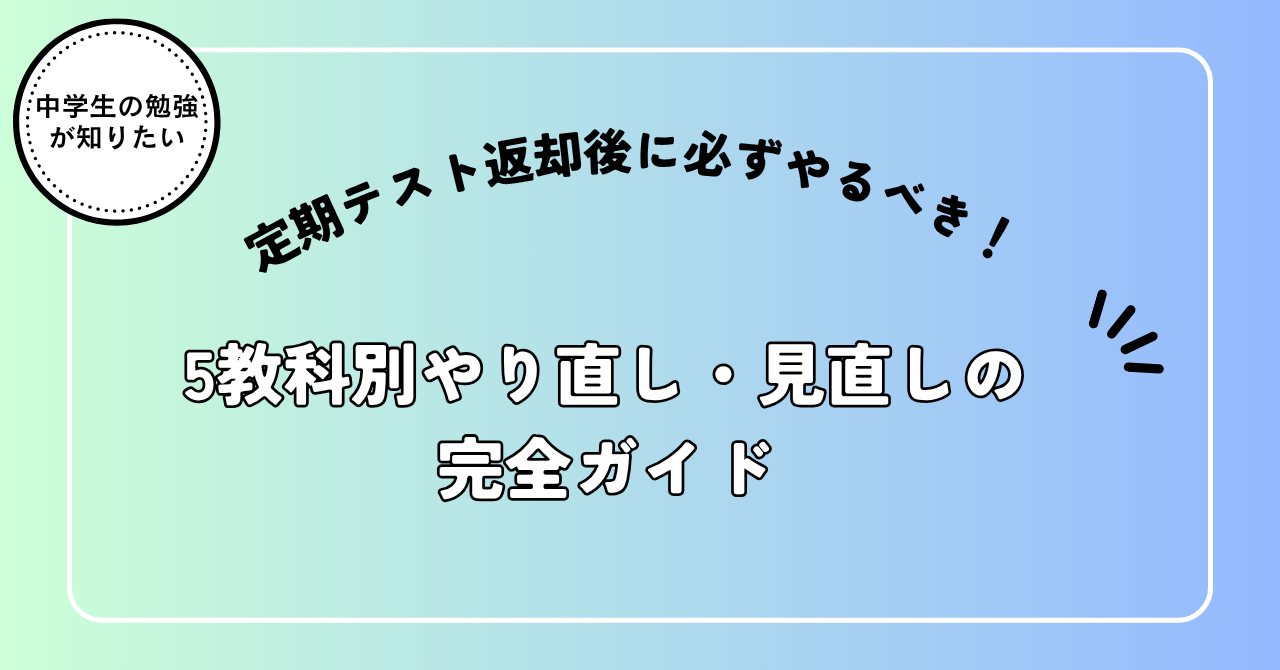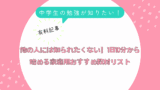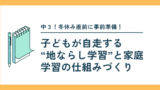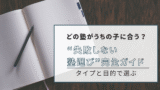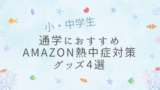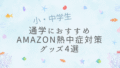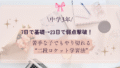こんにちは。学びのインフォです。
定期テストが返ってきたとき、真っ先に気になるのはやはり「点数」ではないでしょうか。
でも、本当に重要なのは点数そのものではなく、「その点数に至った理由」です。
高得点だった子も、あと少しだった子も、見直しの仕方次第で次のテストはもっと良くなります。
逆に、見直しをせずに「終わったテスト」として放っておくと、同じミスを繰り返しがちです。
今回は、『中学生の定期テスト返却後に必ずやるべき!5教科別やり直し・見直しの完全ガイド』をご紹介します。中学生が主要5教科のテスト返却後にどのように「やり直し」を行えばよいか、保護者の方がどんな風に声をかけ、子どもが自力で学び直せるようにするにはどうすればよいかを、具体的にご紹介していきましょう。
やり直しの基本:「なぜ間違えたか?」を自分で考える力を育てよう
やり直しの第一歩は、「なぜ間違えたのか」を自分で考えること。
ここを飛ばしていきなり「正しい答え」を写してしまうと、意味がありません。
自分で間違えた原因を考えることで、次に同じ間違えを繰り返さないように本人の記憶にもより鮮明に残ります。そのためにも、ただ「正しい答え」を写すのではなく『自分で考えること』こそが大切なのです。
保護者ができる“気づかせる声かけ”とは?
以下のような「声かけポイント」を使って、子ども自身にテストを振り返ってもらいましょう。
- この問題は何を問われていたか?
- 自分はどう答えたか?
- どこで間違ったのか?
- なぜそのミスをしたのか?
- 次に同じ問題が出たら、どうすれば正解できるか?
この「ミス分析」は、解き直しよりも効果があります。
一問ずつ原因と対策をメモしていくことで、テストが「学びの宝庫」に変わります。
保護者の方は、正解や解説をすぐ教えるのではなく、「どこが難しかった?」「ここって何と聞かれているのかな?」と問いかける姿勢で接すると、子どもが自力で気づく力を育てることができます。

1人では気がつけないミスもあります。お忙しいとは思いますが、寝る前10分でも構いません。お子様のテスト用紙を点数ではなく、「ミス分析」に時間をあててみるとお子様への声かけもひと工夫出来ると思います。
やり直しの鉄則:5教科それぞれに合った復習方法
ミスの原因分析ができたら、次は教科ごとに適したやり直し方法に進みます。
ここでは、主要5教科それぞれの見直しのポイントを解説します。
国語:設問の読み違えと記述の見直し方法
国語でのミスは、「本文は読めていたのに、設問の読み取りが甘かった」というケースがよくあります。
例えば「筆者の意図」「登場人物の気持ち」「理由を述べよ」といった問いの種類ごとに、どう答えるのが適切かを確認しましょう。
また、記述問題のやり直しは「模範解答を写す」のではなく、「なぜ自分の答えではダメだったか」を理解することが大切です。
やり直し方法
- 自分の答えと模範解答を比べ、言葉の選び方や表現のズレを分析する
- 設問のキーワード(「理由」「根拠」「具体的に」など)を意識する
- 音読して文章構造を把握するのも有効

自分の答えのダメだったところが解らない時は、担当の先生に質問することも大切です!
数学:計算ミスと理解不足を見極める復習法
数学では「ケアレスミス」と「理解不足」が大きな分かれ道です。
「途中式を書いていない」、「問題文の条件を読み飛ばした」などのケアレスミスは、見直しで必ず防げるようになります。
一方で、「公式の使い方」や「解法のステップが理解できていない」場合は、解説を読み、似た問題を解く反復練習が効果的です。
やり直し方法
- 間違えた問題をノートに1問ずつ写し、手順を丁寧にやり直す
- なぜその式に至ったのか「考え方」を言葉で書く
- 同じ単元の似た問題を3問ほど解いて、定着させる

自分がどうして間違えたのかを考え、間違えない為のポイントなどを書き込む
【定期テスト間違い直しノート】を作成して活用するといいです!
英語:文法・語彙ミスの正しいやり直し手順
英語のミスは、「単語のつづりミス」「文法の混同」「語順ミス」など、ルールの理解と暗記がカギになります。
中でもよくあるのが「三単現のs」「時制の一致」「前置詞の使い方」などの細かいルールです。
書いて覚えるだけでなく、音読やシャドーイング(聞いてマネする)を取り入れると定着しやすくなります。
やり直し方法
- 間違えた英文を5回書いて音読
- どんな文法ルールを間違えたかを書き出す
- 単語のミスは単語カードやアプリで復習
理科:用語と計算ミスのタイプ別見直し
理科では「語句が覚えられていない」ミスと、「計算問題ができない」ミスが分かれます。
特に中1〜中2は用語の正確な理解と記述力が問われるため、ただ暗記するだけでなく、意味を整理することが重要です。
また、グラフの読み取りや作図など、形式に慣れる練習も大切です。
やり直し方法
- 用語ミスは「なぜその語を選んだか」を確認し、正しい定義をノートにまとめる
- 計算ミスは式の立て方や単位のミスを確認
- 作図問題は手順ごとにポイントを書き出す
社会:暗記+資料問題の“つまずき”対策
社会は「覚えれば点が取れる」と思いがちですが、実際は「なぜその出来事が起きたか」「地図や資料を読み取れるか」が問われる場面も多くあります。
特に記述式や選択肢問題では、「用語の意味」や「関係性まで理解しておく」必要があります。
やり直し方法
- なぜその選択肢が正解か・不正解かを理由づける
- 時代の流れや地理的特徴を「つながり」で復習
- 覚えにくい用語はゴロ合わせや図で工夫
やり直しの鉄則:親が“答えを教えない”サポートが子どもを伸ばす
テストのやり直しは、子どもが自力で考えるからこそ意味があります。
保護者としてはつい「ここ違うよ」「こうすればいいじゃん」と言いたくなってしまいますが、グッと我慢して「考える材料を与える」ことが大切です。
例
- 「どうしてこの答えにしたの?」
- 「問題文、もう一度読んでみようか」
- 「これ、前にも似た問題あったよね?」
このような“気づかせる声かけ”は、子どもに考えるきっかけを与え、【やり直し力=自己修正力】を育てます。
また、やり直しをしたノートやプリントを「がんばってるね」と認めるだけでも、子どもにとって大きな励みになるので積極的な声かけをしていきたいですね。
よくあるミス5教科別・具体例とやり直しの工夫
各教科2例ずつの見直し実例で具体的にサポート
【国語】
- 設問「理由を述べよ」で「~だから」が抜けて減点 → 文末表現を見直す練習
- 漢字ミス → 自作の「苦手漢字リスト」を作成
【数学】
- 分数の計算で通分ミス → 基本ルールを復習
- 問題文の「図は正確ではない」に気づかずミス → 問題の注意書きにマーカー
【英語】
- 単語の綴り間違い(ex:becase → because) → 書いて発音する練習
- 疑問文に肯定文で答える → 疑問詞・語順を口頭練習
【理科】
- 質量保存の法則で左右の重さが合っていない → 表の作成でチェック
- 用語「蒸発」と「沸騰」を混同 → イラストで違いを整理
【社会】
- 国名と首都を取り違え → 白地図に書き込み
- 歴史の年代順でミス → 時系列カードで並べ替え練習
おわりに:「やり直し力」は受験にも役立つ!
いかがでしたか?今回は、『中学生の定期テスト返却後に必ずやるべき!5教科別やり直し・見直しの完全ガイド』をご紹介しました。
テストの点数は一時的なものですが、「やり直す力」「原因を自分で探す力」は、一生使える力です。
失敗やミスをどう受け止めて、どう改善できるか――これは勉強だけでなく、部活や人間関係、将来の仕事でも求められるスキルです。
テストが返却された日こそ、成長のチャンス。
保護者として「もう一度見直してみよう」と寄り添ってあげるだけで、子どもは自分で「できる子」へと変わっていきます。
次のテストは、やり直した分だけ伸びているはずです。
保護者の関わり方ひとつで変わるかもしれないのであれば、“やり直し力”を育てるためにまずは声かけの1歩を踏み出してみませんか?
お役に立てる情報があったなら嬉しいです。