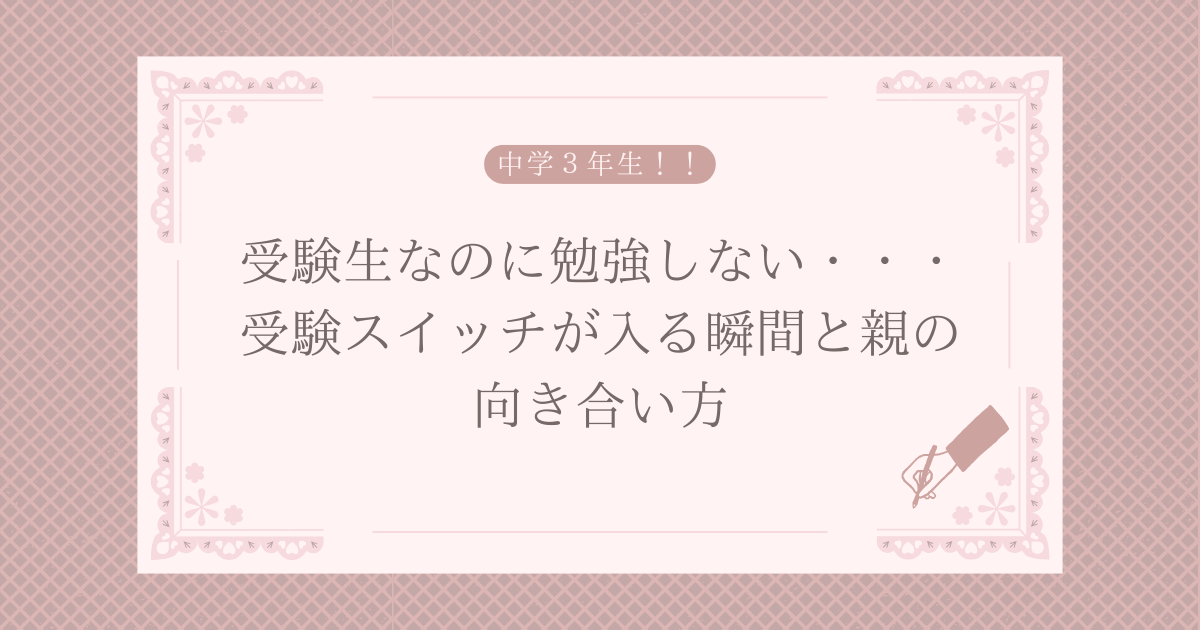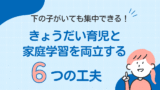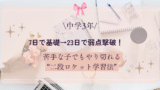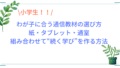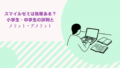こんにちは。学びのインフォです。
「受験生なのに全然勉強しない」――中学3年生の保護者であれば、一度は口にしたことがあるのではないでしょうか。机に向かわずにスマホばかり触っていたり、声をかければ「うるさい!」と返されてしまったり。親としては焦りと不安が募りますよね。
高校受験は人生で最初の大きな試練。親としては「早く勉強を始めてほしい」「スイッチを入れてほしい」と願うのが当然です。ところが、思春期の子どもは親の期待通りには動きません。むしろ、言えば言うほど逆効果になってしまうことも多いのです。
今回は、『受験生なのに勉強しない・・・受験スイッチが入る瞬間と親の向き合い方』をご紹介します。受験生なのになぜ勉強しないのか、その背景や心理を解説しつつ、受験スイッチが入る瞬間、そして反抗期の子どもにどう向き合っていけばいいのかを一緒に考えていきましょう。最後には、家庭でできる受験スイッチを押す環境づくりも紹介していますので、良かったら参考にしてください。
中学3年生が勉強しない本当の理由
思春期特有の心理的背景
中学3年生は心身ともに大きく変化する時期です。
自立心が芽生え、親からの干渉を嫌うようになります。親にとっては「勉強しなさい」と声をかけることは当たり前でも、子どもにとっては「支配されている」と感じることがあります。その結果、わざと机に向かわない態度を取ってしまうこともあるのでしょう。
受験が自分事になっていない
志望校がまだ決まっていない子どもにとって、受験は漠然とした遠い話。
親がいくら「勉強しなさい」と言っても、本人の中に「なぜ勉強するのか」の明確な理由がなければ動けません。「高校に行けるのは当たり前」と思っている子ほど危機感が薄い傾向にあります。

良い機会なので、高校に行ったその先の話をイメージできるような将来の話をしてみるのもおススメです。
勉強から逃げる心理
「勉強しない」の裏には「勉強ができないから避けている」というケースもあります。テストで点が取れない、問題が難しいと感じると、挑戦すること自体をやめてしまうのです。
これは決して怠けではなく、自己防衛の一つ。親としては責めるのではなく、苦手科目を一緒に確認してあげる視点が必要です。

どんなところが解らないのか、苦手としているのかをそれとなく聞いて否定はせず、「じゃあどうしたら良いのか?」というのを話し合えると良いかもしれません。
生活の誘惑要因
スマホやゲーム、SNSは中学生にとって最大のライバルです。友達とのつながりや娯楽が優先され、勉強は後回しになりがち。特に「一度手に取るとやめられない」という依存性があり、保護者の悩みの種になっています。

大人も欲求に負けてしまうことは多々あります。子どもだって同じです。そこを責めるというよりも、物事の優先順位をつける習慣づけとして、やりたいものはやらなければならない事を終わらせた後にするというルールを設けるのはどうでしょうか。
受験スイッチが入る瞬間とは?
「うちの子のスイッチはいつ入るの?」と不安になる保護者は多いですが、実はそのタイミングは人によって大きく違います。
よくあるスイッチのきっかけ
- 模試や定期テストで現実を知ったとき
→ 偏差値や順位を突きつけられ、初めて危機感を覚える。 - 志望校が具体的に決まったとき
→ 「あの学校に入りたい」という目標が明確になると一気に集中力が増す。 - 友達やライバルの頑張りを知ったとき
→ 周囲の勉強量を目の当たりにして焦りを感じるかもしれません。 - 三者面談で先生に現実を伝えられたとき
→ 親の言葉よりも、第三者の言葉の方が響きやすいとも言われます。
遅い子でも大丈夫
スイッチが冬休みや直前期に入る子も珍しくありません。大事なのは「遅い=手遅れ」ではないということ。集中力が高まれば、短期間で成績を伸ばす子も多くいます。保護者は焦らず、子どものペースを信じる姿勢が必要です。
声かけとして避けたい対応
焦るあまりに、ついこんな言葉をかけていませんか?
- 「〇〇くんは勉強してるのに!」 → 比較は子どものやる気を奪います。
- 「このままじゃ落ちるよ!」 → 不安をあおると逆効果。
- スマホを強制的に取り上げる → 信頼関係が壊れる危険性。
- 小さな努力を無視する → 子どもは「どうせ何をやっても認めてもらえない」と感じる。
避けたい対応の共通点は「子どもの自尊心を傷つける」こと。思春期の子は特にプライドが強く、傷つきやすい存在です。親の言葉が、良くも悪くも子どもに大きな影響を与えると意識しましょう。
思春期&反抗期の子への向き合い方って?
命令ではなく提案をしてみましょう
- ×「今すぐ勉強しなさい」
- ○「今日は英語と数学、どっちからやる?」
選択肢を与えることで、子どもは「自分で決めた」と感じやすくなります。
親は監督ではなくサポーターに徹する
保護者は「勉強の監視役」ではなく「応援団」の立場に回ることが大切です。「今日少しでも頑張ったね」と声をかけるだけで、子どもの気持ちが大きく変わることもあります。
勉強以外の会話を大切に
勉強の話ばかりしていると、子どもは「親と話す=小言」と結びつけてしまいます。たわいない雑談や共通の趣味を持つことで信頼関係が強まり、結果的に勉強にも前向きになります。
コミュニケーションの問題は思春期だと大変ですよね。忙しい時間の中、家事の手を止めて子供の話を聞いてあげることも時には大切なようです。

私は以前上の子に、「お母さんはどんな時でも手を止めて話を聞いてくれるところが凄いなって思ってるよ」と言われたことがあります。
正直自分では普段の話なので、子供がそんな風に感じているとは想像もしていなかったので、ちょっと嬉しかったです。
距離を取る勇気
毎回衝突していては疲弊してしまいます。子どもが荒れているときは無理に向き合わず、そっと距離を取るのも一つの方法です。

お互いが1人の人間なので、衝突することもあります。自分の身と精神を守るためにも、たまには距離を取って自分の時間に充てることもお互いのストレス軽減になるかもしれません。
家庭でできる受験スイッチを押す環境づくり
学習環境を整える
リビングの一角に勉強机を置いたり、スマホを一時的に親が預かったりするだけでも集中度が上がります。
ご兄弟がいると、学習環境を整えることにも限度がある場合がありますよね。良かったら、こちらものぞいてみて下さい。
小さな目標を積み重ねる
「1日15分」「ワーク1ページ」など、達成しやすい目標を設定。
小さな成功体験が自信につながり、勉強習慣が定着します。
一緒に計画を立てる
「この教材を何月までに終わらせようか?」と子どもと相談しながら決めると、自主性が育ちます。
親だけが計画を立てて押し付けると反発されやすいので注意が必要です。
カレンダーなどに、大まかな学習計画を立てて、達成できたら子ども本人がチェックを入れたり、シールを貼ったりと視覚化することで達成感を得られるのでおススメです。

一緒に相談しながら計画を立てると、自然と信頼関係も深まるかもしれません
成功体験を増やす教材の工夫
- 基礎から確認できる教材
- 短時間で解ける問題集
- 解説がわかりやすい参考書
こちらでご紹介しているものも参考にしてみて下さい。
模試や過去問で現実を知る
模試は子どもにとってショック療法になることもあります。点数が悪いほど危機感が強まり、やる気に火がつくケースが多いのです。

せっかく受験した模試を放置していませんか?模試は自分の弱点を知る最強のアイテムです。是非見直し、解きなおしもしておきましょう。
保護者自身の心構えはこの3つ
焦らないこと:親が焦ると子どもにも伝染します。
信じること:スイッチは必ず入ると自分に言い聞かせる。
相談先を持つこと:学校の先生や塾、家庭教師、信頼できるママ友達など、親だけで抱え込まない。

受験生の親というのは精神的に本当にきついものです。思春期の子供との向き合い方やこのままで大丈夫なのか?という不安。1人で抱え込まないで誰かに話を聞いてもらって下さいね。
まとめ
いかがでしたか?今回は『受験生なのに勉強しない・・・受験スイッチが入る瞬間と親の向き合い方』をご紹介しました。
中学3年生が勉強しないのは怠けではなく、思春期特有の心理や未熟さからくる自然な行動です。受験スイッチは子どもによって入るタイミングが違い、早い子もいれば直前になってようやく本気になる子もいます。
親ができるのは、無理にスイッチを押すことではなく、スイッチが入りやすい環境を整えること。そして何より「あなたを信じているよ」と伝え続けることです。叱る親ではなく、支える親であり続けたいですよね。
どうか焦らず、子どもの可能性を信じて寄り添ってあげてください。親の支えが、必ず子どもの背中を押す力になります。
この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。