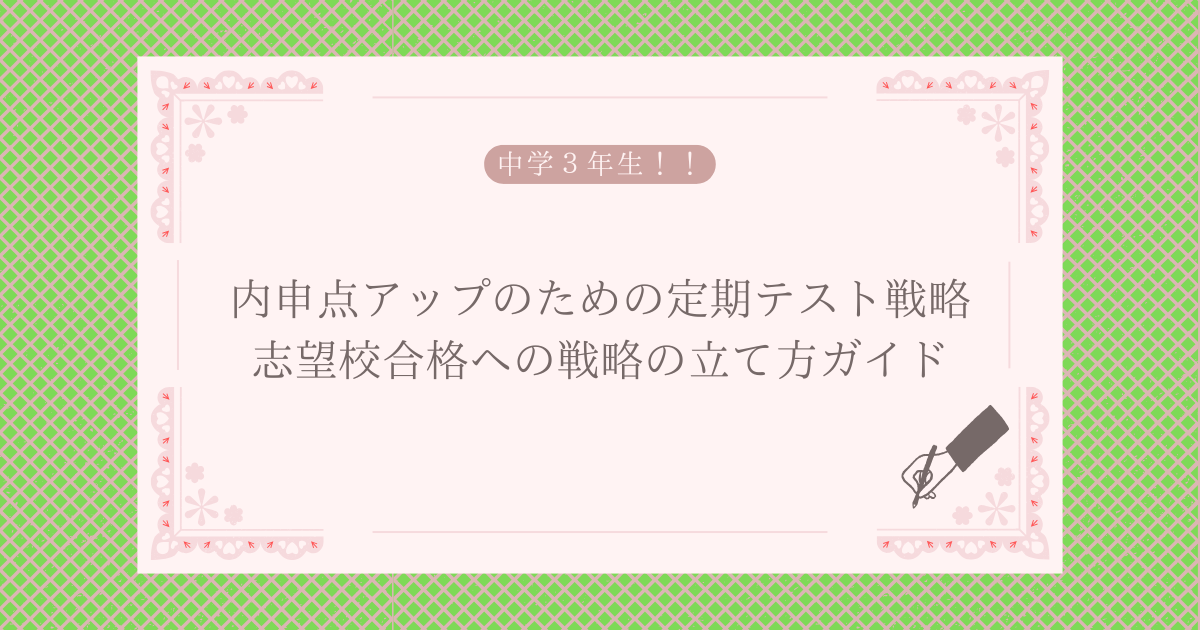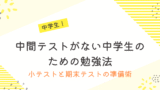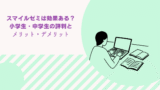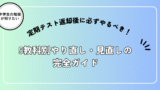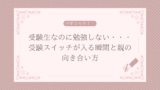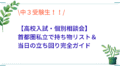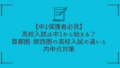こんにちは。学びのインフォです。
「どうしよう。もう時間が足りないのではないか?」
この時期、多くの中学生と保護者の頭をよぎる言葉です。模試の結果に一喜一憂し、提出物の山を前にため息をつき、苦手教科をどう克服すればいいのか悩む…。
私のところにも受験生を抱えたママさんからのお悩みが多く聞こえてくる時期となりました。
そんな不安を少しでも減らすために、この記事では 模試判定の見方・内申点の地域差・苦手教科の落とさない戦略・提出物の効率的な仕上げ方 を一つずつ解説していきます。
「やることは分かってるけど、整理できない」
そんな方こそ最後まで読んでみてください。これから先は、焦ることよりもうまく戦略を立てて苦手なものとどう向き合い、モチベーションを保ったり上げたりして受験勉強をしていくのかにかかっています。
今回は、『内申点アップのための定期テスト戦略|志望校合格への戦略の立て方ガイド』をご紹介しますので、是非情報の一つとして読んでみて下さい。
模試判定の見方と活用法
「この前の模試、C判定だった…やっぱり志望校を変えるべき?」
模試の結果を見たママさんから、こんな声をよく聞きます。
夏休みが終わって、もの凄く頑張って勉強に取り組んでいた子供のママさんほど、模試の結果が想定よりも悪いと不安にかられてしまうのは仕方がありません。
ですが、早々に志望校を変更というのは個人的にはあまりおススメしません。ましてや子供自身が希望して志望校にしていた高校ならば、なおさら志望校の変更をするべきではないと思うのです。
そこで、まずは模試判定の見方と活用法をご紹介しましょう。
模試判定の仕組みを知ろう
模試判定は「志望校の合格可能性」を示すものですが、未来を100%決めるものではありません。
- A判定:合格圏内。ただし油断すると一気に下がる。
- B判定:安定圏。弱点を補強すれば可能性はさらに広がる。
- C判定:努力次第で逆転可能。志望校を諦める必要はない。
- D判定以下:厳しいが「戦略」を取れば突破口はある。
むしろ大切なのは、模試を「実力チェック」ではなく「弱点発見ツールとして活用」することです。
信頼できる模試とは?
模試と一口に言っても、精度や対象はさまざまです。
- 首都圏ならV模擬・進研模試:データが豊富で信頼度高。
- 関西圏なら五ツ木模試:地域に密着しており、受験校選びの参考に最適。

「どの模試を受けるか」よりも「模試をどう復習するか」が合否を左右します。
ボーダーラインを下回ったときの対策
模試でE判定が出ても「終わり」ではありません。ここからが勝負です。
- 国語が弱いなら:漢字・古典文法の小問対策を徹底。
- 数学が苦手なら:計算・小問集合を完璧にして“最低点”を死守。
- 英語が不安なら:毎日の英単語暗記+リスニングで即効性を狙う。

「全部完璧にしよう」とすると挫折します。“落とさないライン”を作ることが逆転合格の第一歩です。
内申点の合否への影響と地域差
模試だけで判断できないのが「内申点」。ここを軽視すると、思わぬ落とし穴にはまることでしょう。
内申点の取り扱い(比重)も地域で差があります。もちろん当日点を高く取れることが一番大切ですが、内申点をおろそかにしても良いという訳ではないのです。
内申点の比重は地域でこんなに違う
- 東京・神奈川・埼玉県:学力検査重視。内申点は約3~4割。
- 大阪・兵庫:内申点の比重が大きい。提出物・授業態度が合否に直結。
- 地方都市:地域によっては「内申点>当日点」というケースもある。

つまり、「同じ模試判定でも、地域によって合格可能性は変わる」のです。
内申点で合否がひっくり返ることも
「模試はC判定だったけど、内申点が高くて合格した」
逆に「模試はB判定でも、内申点が低くて不合格になった」
こんなケースは珍しくありません。多少の地域差はあるものの基本的に内申点というのは軽く考えるべきものではなく、提出物や授業への姿勢を見直すことが大切であることは間違いないでしょう。
苦手教科を落とさないための最低限戦略
「英語が本当に苦手…でも他で稼げば何とかなる?」
このような質問をよくいただきますが、結論から言えば可能です。
第一志望が都立や県立を考えている場合5教科の総合計得点で当日点が決まります。その場合、例えば英語が苦手だったとしても、その他の教科で苦手な教科の足りない得点を補えれば問題ありません。
自分が苦手とする教科と得意な教科(点数が少しでも多く取れる教科)で、総合計を合格ラインに到達することを目標とすれば可能性が見えてきます。では具体的には、どのような戦略を立てれば良いでしょうか。
苦手教科は「足を引っ張らせない」
- 苦手科目は 基礎小問だけを落とさない
- 得意科目は 過去問で安定して点を稼ぐ
このバランスが志望校を合格ラインに持っていくためのカギとなります。
苦手科目だからといって、捨てるのではありません。最低限の努力は怠らないことが大切です。その中で、自分がより得点を取れそうな科目は少しでも得点できるものが増えるように勉強していくことが求められます。
例えば、5教科全体で内申点20が欲しいとします。
- 国語 4
- 数学 5
- 英語 3
- 理科 5
- 社会 3
英語や社会が苦手科目だったとしても、全体で20あれば良いということなのです。
私立の併願優遇や併願確約を取りに行く場合、5教科と9教科どちらかで条件を満たせば良いケースもあります。この場合、主要5教科が少し悪くても副教科でカバーして条件を満たすことも可能です。
つまり、1学期や前期の成績があまり良くない場合は、自分の得意科目に絞って定期テストを頑張ったり、全体の内申バランスを見ながら力を定期テストで力を入れる科目を絞ることも出来るということです。
このような内申点を取るための戦略や入試本番に合格ラインまで持っていく戦略を立てることが、夏休み明けには必要となってくるのです。
教科別の落とさない勉強法
戦略を組み立てたところで、やはり勉強をしなければ結果にはつながりません。
- 定期テストの点数=内申点に直結します
- 学校ワーク・提出物・授業態度も評価対象
そこで教科別の落とさない勉強法の例をご紹介いたします。
- 英語:赤シート+色ペンで英単語・英熟語暗記。リスニングは毎日10分。
- 数学:間違えノートを作り、同じミスを二度としない。公式は全て覚える
- 国語:漢字+短文読解を毎日少しずつ。
- 理科:公式は覚える。最低限の基礎知識は覚える
- 社会:時代の流れを把握する。資料集なども見ておく。
👉 おすすめグッズ:
- 【ノートまとめ教材】 → 復習ノートを効率的に仕上げられる
- 【赤シート】 → 単語暗記の定番(下敷きサイズが意外と使えます)
- 【色ペン】 → 多少の使い分けで提出物も完成度アップ
定期テスト対策はこちら
苦手教科の補強に意外と役立つ通信教材
提出物を効率的に仕上げる方法
定期テスト直前、意外に時間を奪うのが「提出物」です。
提出物が内申点を動かす理由
学校ワークの提出状況は、先生からの「評価=内申点」に直結します。期限を守るだけで印象は大きく変わります。定期テスト前でも、課題やワークを期限通りに提出することは必須です。
効率化のコツと便利グッズ
- タブレット教材やTODOリストで課題を一元管理
- 赤シート+色ペンで清書しながら暗記
- ノートまとめ教材で提出用ノートを時短作成

特に赤シートは「提出物の清書」と「暗記」が同時にできる万能アイテム。受験生なら必ず持っておきたいグッズです。
志望校合格に向けた当日点戦略
またこの時期に志望校合格に向けた当日点戦略も立てておきましょう。
- 志望校の過去問で目標得点を設定する
- 「内申点が不足気味な場合の当日点シミュレーション」
県立高校を目指している場合は、受験したい学校の合格ボーダーラインというものがあると思います。そのボーダーラインに5教科でどう得点を取っていくのが現実味あるかという戦略を立てましょう。そこに自分の内申点を考慮し、内申点が低めの人は当日点を多く取ることが出来るように戦略を立てることが必要です。
当日点を伸ばす3つの柱
- 基礎問題で落とさない
- 得意科目で稼ぐ
- 苦手科目は「捨て問」を作らない
定期テストが終わったら必ずやりましょう
まとめ
いかがでしたか?今回は、今回は、『内申点アップのための定期テスト戦略|志望校合格への戦略の立て方ガイド』をご紹介しました。
大切なのは「戦略的に取捨選択すること」です。
- 模試判定は弱点発見に使う
- 内申点から当日点を逆算する
- 苦手教科は落とさないラインを守る
- 提出物は勉強グッズで効率的に行う
受験勉強はマラソンに似ています。最後の直線でペースを乱さず、戦略的にゴールを目指すことが何より大切です。
まだまだ受験スイッチが入らない!というお子様もいるかと思われます。焦る気持ちは親ばかり・・・。誰しもが通る受験生を持つ親の不安ですよね。だからこそ、今すべきことを整理し、1つずつ着実にクリアしていきたいですね。
この記事が少しでもみなさまのお役に立てれば嬉しいです。