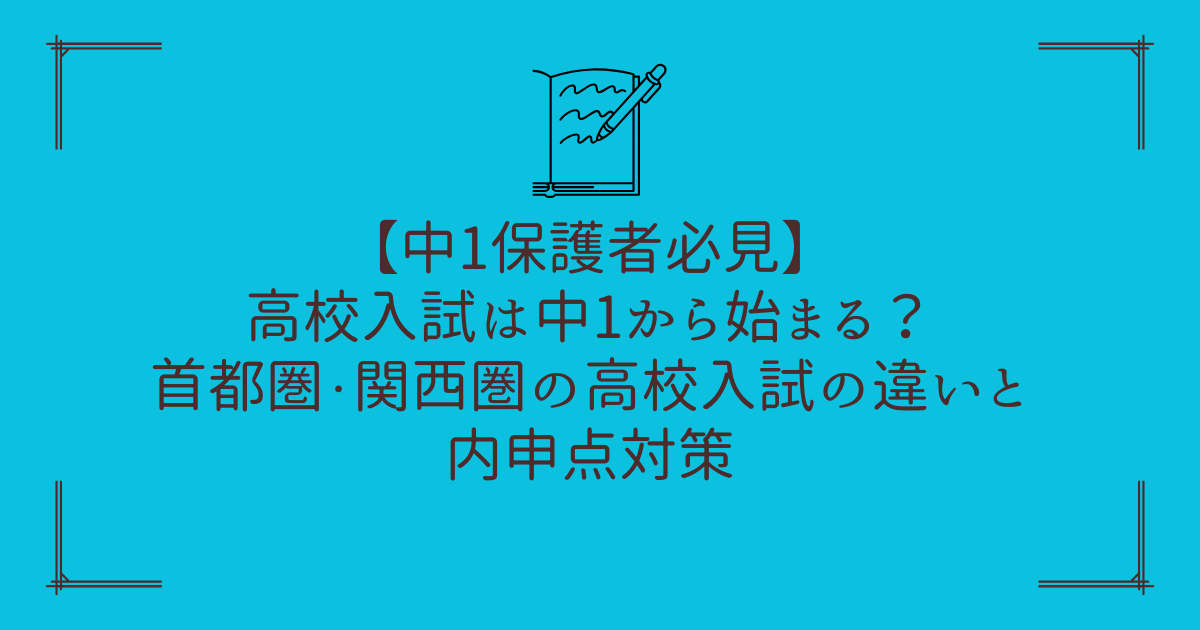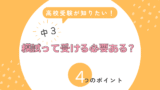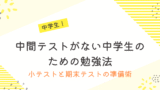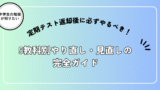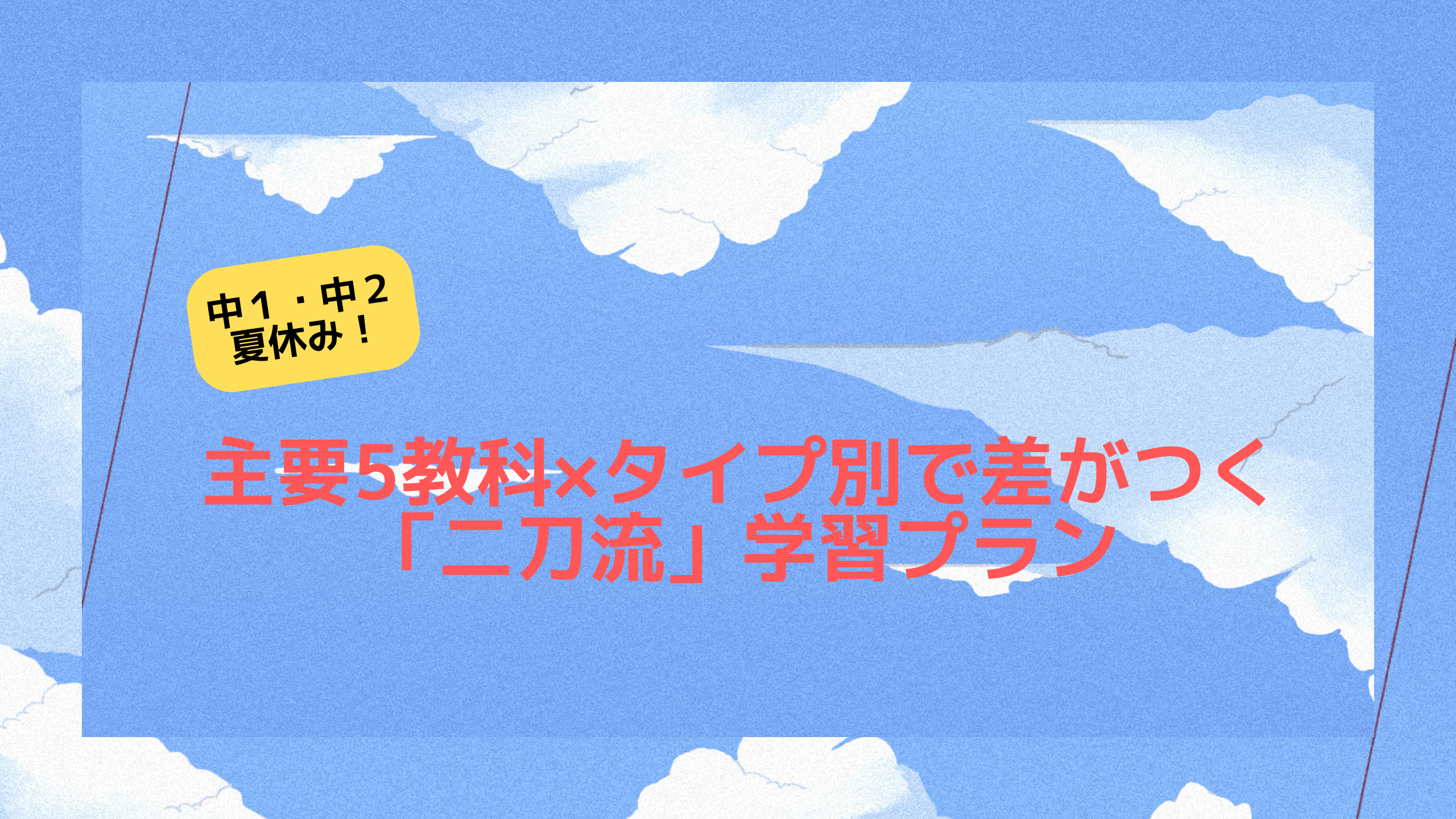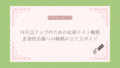こんにちは。学びのインフォです。
中学1年生のお子さんを持つ保護者の方にとって、「高校入試」という言葉はまだ少し先の話に感じられるかもしれません。
しかし実際には、高校入試の仕組みを早く理解しておくことで、中学生活全体の過ごし方や学習の取り組み方に大きな違いが出てきます。
特に 首都圏と関西圏では、高校入試の仕組みや合否の決まり方が大きく異なる ため、「うちの地域ではどうなっているのか」を早めに知っておくことが重要です。
今回は『高校入試は中1から始まる?首都圏・関西圏の高校入試の違いと内申点対策』をご紹介します。首都圏と関西圏の高校入試制度の違いをわかりやすく整理しつつ、中学1年生の段階で保護者が意識しておくべきポイントを具体的に紹介します。
高校入試制度の基本を押さえよう
高校入試ってどんな感じだったかな?多くのママさんたちが、昔を振り返ってもあまり思い出せなかったり、時代とともに変化している高校入試を知らなかったりしていますよね。
まずは、高校入試制度の基本を知ることから始めてみましょう。まず押さえておきたいのは、地域ごとに入試制度が大きく異なるという点です。
昔は中学校の先生が先導して志望校を決めていたという地域でも、今は親が主体になって動くことがある地域も増えてきています。
高校入試は大きく「公立高校」と「私立高校」に分けられます。
- 公立高校入試
各都道府県の教育委員会が定めた方式で行われ、基本は「学力検査(筆記試験)+内申点(通知表)」で判定します。 - 私立高校入試
各学校が独自に実施する方式で、筆記試験・面接・作文など内容は多様です。
また、多くの地域では「推薦入試」「一般入試」の2種類があります。推薦は内申点や面接重視、一般は筆記試験中心という形が一般的です。
この基本構造は全国共通ですが、首都圏と関西圏では入試回数や内申点の比重に大きな違い があります。
首都圏の高校入試の特徴
ではまず、首都圏の高校入試の特徴を見てみましょう。
首都圏といっても東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で制度は異なります。
- 東京都
東京都の公立高校入試は「推薦入試」と「一般入試」の大きく2つの方法で行われます。多くの受験生が一般入試に挑みますが、推薦入試も重要な選択肢となっています。 - 神奈川県
神奈川県の公立高校入試では、全員が「共通選抜」を受験します。共通選抜では、学力検査の得点と調査書(内申点など)の評価を基に算出した「S値」と呼ばれる総合得点によって合否が決まります。 - 千葉県
千葉県の高校入試の合否判定は、主に「総得点による選抜」と「2段階選抜」の2つの方法があります。 - 埼玉県
埼玉県公立高校の選抜は、「学力検査」と「調査書」が中心となります。高校によっては、面接や実技検査が実施されることもあります。
こんな特徴も
- 公立高校入試は「都県ごとに制度が異なる」
例:東京都は内申点の比率が高く、神奈川県は学力検査の比率が高め。 - 私立高校は「併願優遇」や「併願確約」が広く利用されている。
- 模試の志望校判定が活用しやすく、進路指導で利用されることもある。

首都圏は「内申点重視」が顕著です。中学1年生の成績から高校入試に反映される地域もあるため、早い段階から提出物や授業態度を意識しておく必要があります。
関西圏の高校入試の特徴
次に関西圏の高校入試の特徴を見てみましょう。
関西圏(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)もまた多様です。
- 大阪府
大阪府の公立高校入試は、学力検査と調査書(内申点)が主な選抜資料となります。これらに加えて、自己申告書や、特別選抜では実技検査や面接が加わります。 原則として1校1学科への出願ですが、募集人員を複数の学科ごとに設定している高校では、他の1学科を第2志望として出願することができます。例えば、同じ高校の普通科と英語科がある場合、第一志望を英語科、第二志望を普通科という形で出願可能です。 - 京都府
「前期・中期・後期」と3回の入試があるのが特徴。チャンスは多いものの、スケジュールが長期化するため集中力が求められます。 - 兵庫県
兵庫県の公立高校入試は、大きく分けて「推薦入学・特色選抜」と「一般選抜」の2つの主要な制度で行われます。 - 奈良県
2026年度入試から、奈良県立高校の入試制度は大きく変わります。この変更は、受験生の能力や適性をより適切に評価し、多様な進路選択を支援することを目的としています。
変更点その1:一次選抜への一本化
これまでの「一般選抜」と「特色選抜」は別々に実施されていましたが、新制度では「一次選抜」として一本化されます。
変更点その2:調査書の評価対象拡充
調査書の評価基準も見直され、従来は中学2年生と3年生の成績が反映されていましたが、新制度では中学1年生の成績も評価対象に含まれるようになります。
- 滋賀・和歌山 「一般選抜」と「特色選抜」という仕組みがあり、学力検査以外に面接・実技などで多様な力を評価されます。
こんな特徴も
- 公立高校入試は府県単位で制度が統一されていることが多い。
例:大阪府は当日点重視、京都府は3回入試のチャンスがある - 私立高校は「専願」「併願」で出願方法を明確に区分している。
- 内申点の取り扱い方が首都圏に比べてややシンプル。

「受験機会が複数回ある県もある」ことが大きな特徴。模試や過去問演習で本番慣れを重ねることが、合格の決め手になります。
内申点が合否に与える影響
高校入試で最もママさん達が気になるのは「内申点がどれだけ合否に影響するのか」という点ですよね。
内申点が高校入試の合否に与える影響は、関東圏と関西圏でその考え方や比重が異なります。各地域の制度や文化によって特色がありますので、ちょっと見てみましょう。
関東圏:内申点が高ければ有利な傾向
関東圏、特に東京都、神奈川県、埼玉県などでは、内申点が高校入試の合否に与える影響が大きい傾向があります。
併願優遇制度による影響
- 私立高校の併願優遇: 関東圏の多くの私立高校では「併願優遇」という制度が発達しています。これは、「内申点(評定平均)が〇〇以上」といった出願基準を満たし、中学校との事前相談などを経ていれば、公立高校が不合格だった場合にその私立高校への入学が確約される、というものです。この制度を利用することで、受験生は安心して公立高校に挑戦できるため、内申点が合否に直接的かつ大きな影響を与えます。
- 公立高校でも影響は大きいケースも: 都道府県によって異なりますが、公立高校においても内申点の比率が高い地域では、内申点が1ポイント違うだけで合否が逆転する可能性もあります。
関東の内申点の算出方法
9教科×5段階評価=45点満点が標準で、そこに学力検査の点数がプラスされて合否判定されるのが一般的です。中学2年生や3年生の成績が特に重視されることが多いですが、中学3年生の2学期の成績が最終的な内申点に最も大きく影響すると言われています。
関西圏:当日点や特色選抜が重視される傾向
関西圏では、内申点の扱いや合否への影響が、府県ごとの独自の制度や入試形式によって大きく異なります。
都道府県ごとの多様な比重
- 大阪府: 当日実施される学力検査の得点が重視される傾向が非常に強いです。内申点と学力検査の比率は高校ごとに「3:7」から「7:3」まで設定されていますが、難関校ほど学力検査の比重が高く設定されます。内申点が多少低くても、入試当日の学力検査で高得点を取れれば挽回できる余地が大きいです。
- 兵庫県: 学力検査と調査書(内申書)の点数を同等に扱う高校が多いです。当日点(学力検査)と内申点の比率が1:1となるよう調整され、さらに第一志望校には25点の加算点があるのが特徴です。
- 京都府: 中期選抜では学力検査と報告書(内申点)の比率がおおむね1:1となっています。前期選抜では、面接や作文、実技などが重視される選抜方式もあるため、内申点だけでなく多角的な評価が求められます。
- 奈良県: 2026年度入試からは新制度が導入され、学力検査と内申点の比重は高校が選択できるようになり、3:7から7:3の範囲で設定されます。中学1年生の成績も評価対象に含まれるようになり、日頃の学習態度がより重視されるようになります。
関西の内申点の算出方法
関西では、内申点の計算方法自体が府県ごとに異なります。
- 大阪府: 「5段階評価×9教科=45点満点」を基本としつつ、特色選抜では特定科目を重視したり、芸術系コースでは実技の比重を上げたりと、学校ごとにカスタマイズされている印象です。
- 和歌山県: 中学3年生の評定は2倍して計算されるため、中3の成績が最も重視されます。
特色選抜・推薦入試の違い
関西圏では、特色選抜や推薦入試がより多様で、内申点だけでなく、面接、小論文、実技、活動実績などが合否に大きく影響します。私立高校の推薦入試においても、関東のように「内申点だけで合格」というケースは少なく、一般入試の科目をしっかり解かせる学校が多い傾向にあります。

首都圏では「通知表=合否に直結」する割合が高いのに対し、関西圏は「当日点勝負」の色合いが強いといえます。中3は、一学期と二学期で総評価がつきます!
中1から意識すべき「定期テスト戦略」
内申点を左右する最大の要素は、定期テストの結果です。もちろん毎日の授業態度や提出物も大きく影響する場合があります。ですがやはり、定期テストで点が取れないとせっかくの苦労も水の泡になってしまいます。
定期テストの積み上げがカギ
- 中1の時点で「オール3」と「4・5が多い通知表」では、高校受験時に大きな差となる。
- 特に首都圏では、私立併願確約の条件を満たせるかどうかが定期テストで決まる。
戦略的に狙うべき科目
- 英語・数学 → 高校入試でも得点差が出やすい。
- 苦手科目 → 極端に2を取らないように「最低限の底上げ」が必要。
- 実技教科 → 内申点の比率で2倍扱いになることがある(東京都など)。

中1から「テスト前だけでなく、毎日の授業理解を積み重ねること」が最重要です。
模試判定の見方と信頼できる模試
中学1・2年の段階でも、模試は「現在地を知る」ための有効なツールです。受験可能な模試がある場合には、自分の現時点の学力を知る為と、苦手としている単元を見つける為にも受験することをおススメします。
模試の活用法
- 偏差値だけでなく合格可能性(判定)をチェック
A判定=80%以上、B判定=60%以上が目安。 - 偏差値の数値よりも「弱点科目の特定」に使う。
信頼できる模試
- 首都圏:Vもぎ、Wもぎ、駿台模試。
- 関西圏:五ツ木模試、進研Vもし。

模試を年に数回受けて、弱点補強に活かすことで「伸びる学習」を身につけましょう。
提出物・内申対策の工夫
意外と見落とされがちなのが 提出物や授業態度です。首都では内申点が合否に関わることもあるので、中1から出来ることとして普段から心がけておくことで受験への土台が組み上げられていきます。
- 提出物は「期限を守る・抜け漏れなく」を徹底するだけで評価は上がる。
- 実技科目では「授業中の姿勢」が内申に直結。
- ノートは丁寧に書いてまとめる
よくある失敗と成功例
失敗例
- 「中3から頑張ればいい」と思って、中1・中2の成績を軽視 → 内申点不足で志望校を諦めるケース。
- 「内申点ばかり気にして模試を受けない」 → 本番の雰囲気に慣れず失敗。
成功例
- 中1から提出物を習慣化 → 安定して高い内申点をキープ。
- 模試を受験本番前に1回は受験 → 本番の緊張に強くなり、実力を発揮できた。
保護者が押さえておくべきポイント
中1保護者にとって大切なのは「長期的な視点を持つこと」です。
- 首都圏では「通知表が入試に直結する」ため、中1からの積み上げが重要。
- 関西圏では「当日点重視」なので、模試や過去問演習で実力を高める必要がある。
- どちらの地域でも「最低限の内申点+当日点で合格ラインに届く戦略」を持つことがカギ。
毎日の家庭学習や定期テストのやり直しは大切です
まとめ
いかがでしたか?今回は『高校入試は中1から始まる?首都圏・関西圏の高校入試の違いと内申点対策』をご紹介しました。
そもそも「昔と制度が変更されていて、今の高校入試が解らない!」という声や「結婚してからこの地域に住んでいるけれど、入試の制度ってどこも同じじゃないの?」というママさん達の声をよく聴きます。
難しいですよね。ここ数年で新しく変更されたり、これから制度が変わる県もあるのですから仕組みをよく調べないと、ついていけないかもしれません。
中学1年生の今だからこそ、入試の全体像を理解し、将来を見据えた学習習慣をつくることがいざ受験生!となったときに慌てずに済むと思います。
この記事が少しでもみなさんのお役に立てれば嬉しいです。