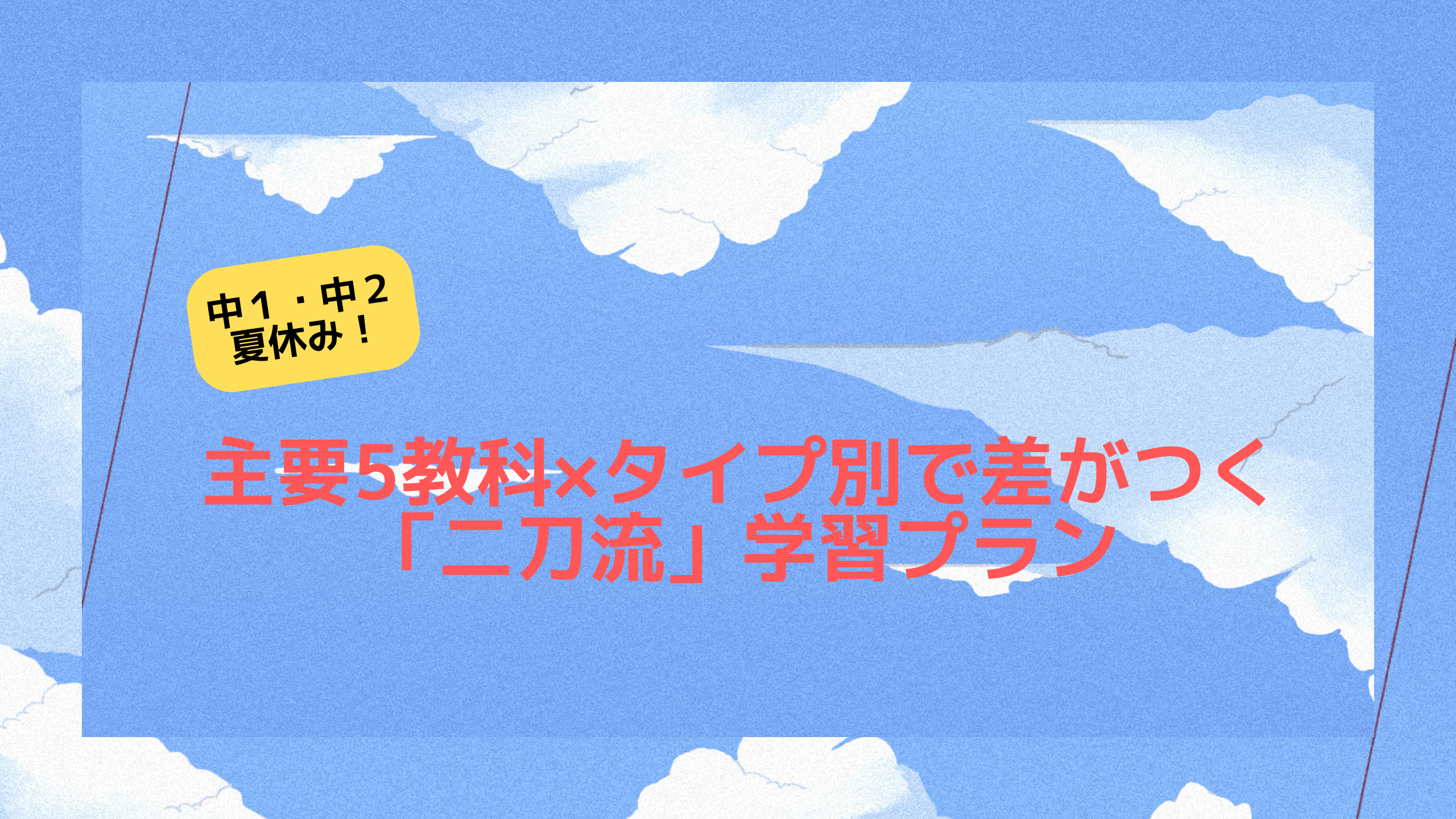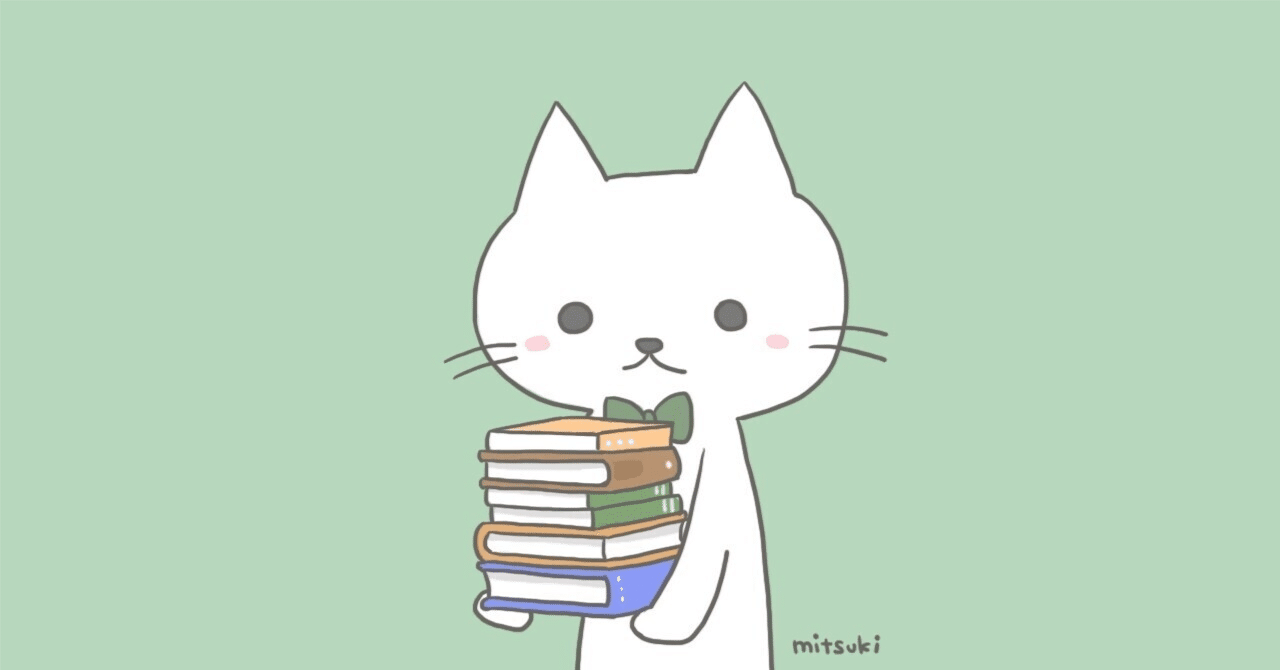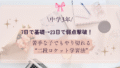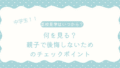こんにちは。学びのインフォです。
そろそろ定期テストが終了し、テスト結果が返却されてくるころですね。最近では中間テストが無く、学期に1回のテストと普段行われている単元テストや小テストなどで内申が決まる学校も増えてきているようです。
そしてもうすぐ夏休み。返却されたテスト結果を見て、不安に思っている保護者の方も多いことでしょう。夏休みは、学校の授業が止まるからこそ、自分のペースで弱点克服や得意教科の伸ばしに集中できるチャンスです。でも実際には、「何から始めればいいのかわからない」「勉強しているのに、なぜか成績に反映されない」といった悩みを抱えるご家庭も少なくありません。
特に中学1年生・2年生の場合、部活動も本格化し、勉強との両立に苦労する子も多いでしょう。さらに、同じ中学生でも「勉強が得意な子」と「勉強が苦手な子」では、学習の優先順位や方法がまったく違ってきます。
そこで今回は、「主要5教科それぞれでやるべきこと」を、勉強タイプ別(苦手/中間/得意)にわけて解説。ご家庭での声かけや教材選びにも役立つ「タイプ診断」や「サポートポイント」もご紹介します。
タイプ別診断:うちの子はどのタイプ?
| 質問項目 | YESが多い場合 |
|---|---|
| ・授業中の内容をよくわかっていない ・小テストで平均点を下回ることが多い ・宿題を後回しにしがち | Aタイプ:基礎補強型(苦手) |
| ・教科ごとに好き嫌いがある ・平均点前後は取れている ・集中力にムラがある | Bタイプ:バランス型(中間) |
| ・授業内容はほぼ理解している ・テストで80点以上が多い ・自学自習がある程度できている | Cタイプ:先取り強化型(得意) |
どうでしたか?タイプがわかったら、次は教科別に「この夏にやるべきこと」を具体的に見ていきましょう。
この夏にやるべきこと
英語:単語・文法の“積み上げ”が勝負を分ける
Aタイプ(苦手):聞く・読む・書くを1文ずつ
- 1日10単語の暗記と、例文の音読・書き写し
- 教科書の本文を音読&書き取り(1日1段落)
- 動詞(be・一般動詞)の使い分け復習

「単語の意味はわかるけど、文にできない」という子は多いです。
声に出して“口グセ”にすることで、文のパターンが自然と身につきます。
Bタイプ(中間):文法の型と読解の「つなぎ」を意識
- 教科書内容の文法整理ノートづくり
- 英検5級〜4級の文法問題やリスニング
- 英語日記にチャレンジ(3行でOK)

このタイプの子には「文の構造を理解すること」が大切。学校の授業で習った文法を、自分の言葉で使ってみる練習をしましょう。
Cタイプ(得意):表現力の強化と長文読解へ
- 英検4級〜3級レベルの長文演習
- 英作文・日記の添削トレーニング
- シャドーイングやディクテーション

得意な子ほど、より「実践的なアウトプット」に取り組むことで、応用力が鍛えられます。
数学:基礎演習+応用力のバランスをとる
Aタイプ(苦手):基本計算を繰り返す
- 1日10分の計算ドリル(正確さ重視)
- つまずいた単元の復習(正負の数・方程式など)
- ノートに「間違えた理由」も書く

苦手な子ほど、「基本のミス」を放置しがちです。毎日短時間でも継続して、ミスのパターンを減らすことが大切です。
Bタイプ(中間):応用問題に慣れる練習
- 基本問題→標準問題の順に解く
- 教科書の例題を解き直して理解の深掘り
- 苦手単元は1日1テーマに絞って集中

このタイプの子は「なんとなく解けるけど、応用になるとつまずく」ケースが多いので、ステップを踏んで難易度を上げましょう。
Cタイプ(得意):思考力系問題&先取り
- 入試問題(1行問題)にチャレンジ
- 中3内容の「乗法公式」「関数」など先取り
- 複数の解法を試すトレーニング

ただ解けるだけでなく、「他の方法でもできる?」と考えさせることで、さらに数学的思考が深まります。
国語:すべての教科の“読解力”を育てる
Aタイプ(苦手):短い文からスタート
- 1日1つの短文読解問題
- 音読(5分)とふりがな読書
- 接続語・主語・述語を意識する読解

「国語が苦手=文が読めない」ではありません。まずは文の構造を意識して、読み取る練習を地道に積みましょう。
Bタイプ(中間):記述に強くなる練習を
- 説明文と小説の読み方の違いを整理
- 漢字演習を週3回ペースで
- 要約(5行)や感想文の練習

このタイプの子は、「自分の考えを言語化する」ことが苦手なことも。書いて伝える練習を意識しましょう。
Cタイプ(得意):評論文・記述力強化
- 新聞や時事ネタコラムの要約
- スピーチ原稿作成や作文練習
- 文学作品の読書感想レポート

受験や検定にも通じる「自分の意見を持ち、表現する」力を高めておくと、どの教科にも役立ちます。
理科:実験や動画で“イメージ”をつかむ
Aタイプ(苦手):視覚と経験で理解を補う
- NHK for SchoolやYouTubeの学習動画視聴
- 教科書語句を使った穴埋めドリル
- 簡単な実験(自由研究)に取り組む

理科は現象のイメージができないと苦手になりやすい教科。動画や図で“体験”を増やしましょう。
Bタイプ(中間):2学期内容の予習も視野に
- 苦手単元のまとめノート作り
- 小テスト形式の語句チェック
- 実験→まとめ→演習問題の流れ

バラバラに理解していた知識を「つなぐ」ことで、点が取りやすくなります。
Cタイプ(得意):入試レベルにステップアップ
- 応用問題・記述問題に取り組む
- 難関高校向け理科問題の資料集活用
- 身近な現象を説明する“発表型学習”

“なぜそうなるか?”の理屈まで深掘りすることで、論理的思考力が育ちます。
社会:暗記から“理解”へと進化させよう
Aタイプ(苦手):視覚教材で基礎固め
- 地図帳・資料集で「目で覚える」
- 年表づくり&人物カードづくり
- 覚えた内容を家族に説明してみる

社会が苦手な子は、単純暗記で終わっていることが多いです。「関係性」や「時代の流れ」で覚えるように工夫しましょう。
Bタイプ(中間):つながり重視で整理学習
- 歴史と地理をリンクさせて学ぶ
- 教科書の流れを図式化する
- 資料問題の演習に取り組む

「点」としてバラバラに記憶していた知識を、「線」としてつなげることでスムーズに理解できます。
Cタイプ(得意):記述と背景知識の強化
- 因果関係や背景を説明するトレーニング
- 模擬記述問題に挑戦
- 時事問題×教科書の応用思考

社会は「覚えるだけ」で終わらせない力が求められます。実際に考え、説明することで応用力がついてきます。
中学生におススメの学習教材
日々の勉強でも利用できる、中学生におススメの学習教材のご紹介はこちら。
夏の学習を「見える化」する方法
夏休み学習は、ただ「やる」だけでは成果が見えにくいことも。
そこでおすすめなのが「週ごとのふり返り」と「見える化」の仕組みです。
- 週のはじめに「小さな目標」を決める(例:英単語50語、計算プリント3枚)
- できたことに○をつける「見える進捗表」を作る
- 保護者の一言メモ欄をつけて励ましを
週1ふり返りシート(例)
※ 保護者コメントはあったら嬉しいお子さまもいるかもしれませんが、日付、今日やったこと、自分でつける〇△×だけでも見える化されて良いと思います。
| 日付 | 今日やったこと(教科・内容) | 自分で〇△✕ | わからなかったこと・できたこと | 一言ふり返り(保護者コメント) |
|---|---|---|---|---|
| 〇/〇(月) | 英語:単語20個、音読3回数学:計算ドリル1枚 | 〇 | 英単語の覚えがスムーズ。計算は見直しで1問ミスに気づけた | しっかりやれていたね!特に英語の集中力がすごかったよ。 |
| 〇/〇(火) | 理科:動画で光の屈折、まとめノート作成 | △ | 光の進み方が少しむずかしかった。図を描いてみた | 図にして説明できていたね。わからない所を自分から話せたのも◎ |
| 〇/〇(水) | 国語:短文読解1問、漢字練習5個 | 〇 | 記述問題も書けた!主語と述語に注意した | 文章を丁寧に読んでいて感心しました。 |
| 〇/〇(木) | 社会:歴史の人物まとめ、地図帳チェック | △ | 地名と人物がごっちゃに…もう少し整理したい | いっしょにカードを作って覚えようか!協力するね。 |
| 〇/〇(金) | 数学:比例の予習、グラフ問題 | 〇 | 先取りもできた。グラフの読み取りに手応えあり | よくチャレンジしてたね!伸びを感じるよ |
| 〇/〇(土) | 英語:英検4級リスニング、リピート練習 | 〇 | 聞き取りやすくなった。自信がついた | 発音も上手くなってる!がんばってる証拠だね。 |
| 〇/〇(日) | お休み or 自由学習 | ✕ or △ | ちょっとだらけた…けど1問だけ英語解いた | たまには息抜きも必要!でも1問やったのはすごいよ! |

勉強を続けるには「達成感」が重要です。親子で共有できる仕組みがあると、やる気が長続きしやすくなります。
夏の家庭学習を支える!保護者のサポートポイント
「やることを決める」だけでなく、「決めたことができた」を一緒に確認する
夏休みは時間がたっぷりあるようで、意外と計画倒れになりがちです。
お子さんと一緒に「1日○分だけ」「週に○ページだけ」といった“小さな目標”を決めましょう。
そして、1日の終わりや週の終わりに「できたね」「ここまで進んだね」と一緒に確認することで、達成感が生まれ、習慣化しやすくなります。

ポイント:毎日は難しくても、「週1のふり返り時間」をつくるだけでも効果的!
子どもが「わからなかった」と言える雰囲気をつくる
子どもが勉強を嫌いになる理由の多くは、「わからないのに聞けない」「怒られそうで質問しにくい」という心理的な壁です。
「どこまでやった?」「今日の一番むずかしかったところは?」と聞くようにし、「わからなかったことは悪いことじゃない」と伝えてあげると、自然に学びへの姿勢が前向きになります。

ポイント:「何ができた?」より「何が難しかった?」の質問が◎
教科や内容より「行動」をほめる
たとえば、計算問題を10問解いたことそのものより、「最後まで集中してやったね」「ミスを見直してたね」など、“行動そのもの”に注目して声をかけましょう。
特に苦手教科に挑戦した日には、「チャレンジしたね!」「えらいよ!」と肯定の言葉をかけることがやる気の継続につながります。

ポイント:「やった量」より「やろうとした姿勢」に注目!
教材選びは“子どもと一緒に”
夏の学習教材を親が全部決めてしまうと、子どもは「やらされている」と感じがちです。
一方で「この中から選んでみよう」「どれがやりやすそう?」と子どもに選ばせることで、主体性が育ち、取り組む姿勢も変わってきます。

ポイント:選ばせるときは2〜3択がベスト(例:「この2冊、どっちの方がやりやすそう?」)
「家族との会話」こそ最高のアウトプット
国語や社会、理科などの内容は、日常会話の中で取り上げてあげるだけで、理解が深まることがあります。
たとえば「ニュースで見たアレ、理科の単元と関係あるよね」「これって歴史でやったやつ?」とつなげて話題にするのもおすすめです。
また、子どもが「ねえ聞いて」と自分から話してきたときには、ぜひじっくり耳を傾けてあげてください。話すことで記憶や理解が強化されます。

ポイント:「話を聞くこと=学力の支援」です!
この夏が“変わるきっかけ”になる
いかがでしたか?今回は『中1・中2の夏休み!主要5教科×タイプ別で差がつく「二刀流」学習プラン』をご紹介しました。
勉強が得意な子にも、苦手な子にも、それぞれに合ったやり方があります。そして、どちらの子にとっても「夏休み」は、自分のペースで実力をつける最大のチャンスです。
「復習」と「先取り」のバランスを見極め、家庭でもサポートできる体制を整えれば、2学期の成績や通知表にも確実に変化が現れてきます。
まずは、お子さんの“タイプ”を見きわめることから始めてみませんか?
この夏が、お子さんの「自信」と「可能性」を広げる時間になりますように。
この記事がみなさんのお役に立てれば嬉しいです。