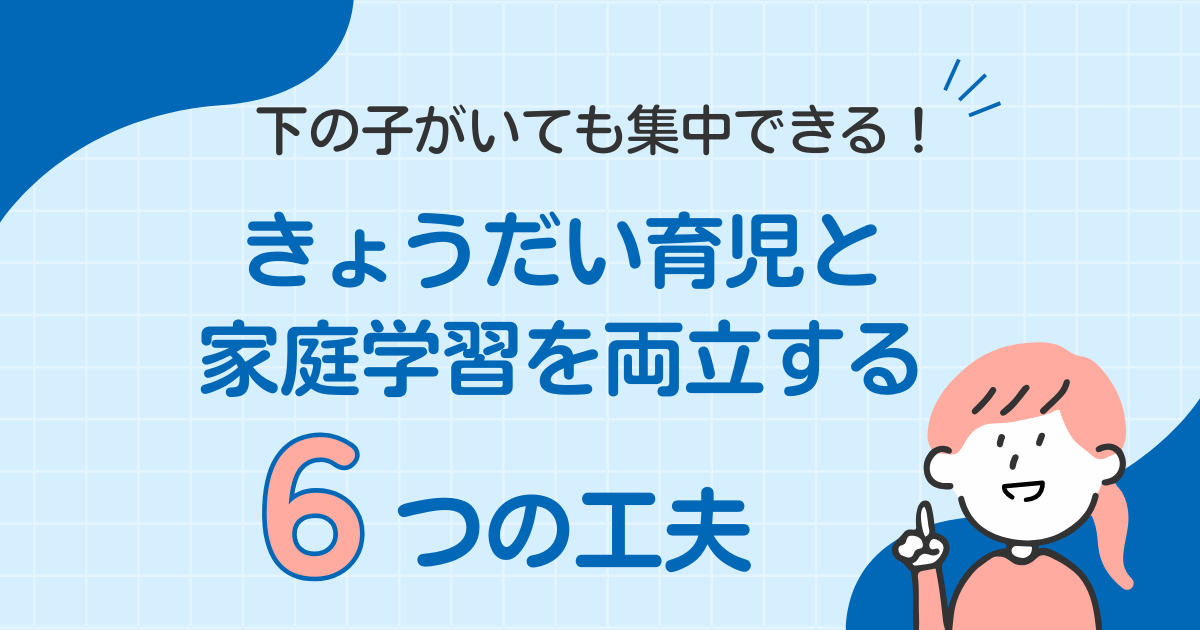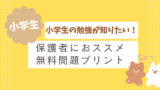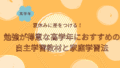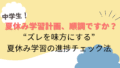こんにちは。学びのインフォです。
「さあ、上の子の宿題に付き合おう!」と思った瞬間、下の子が「遊んで〜!」と割り込んでくる…。結局、上の子は集中できずにイライラ、下の子は泣き出して、保護者は怒鳴り声で一日を終える——そんな毎日になっていませんか?
年齢差のある兄弟・姉妹を育てながら家庭学習に取り組む保護者にとって、「学習」と「育児」の両立は想像以上にハード。ですが、ちょっとした工夫で、両方をバランスよく進めることは可能です。
今回は、小学生の家庭学習をめぐるきょうだいトラブルを減らし、下の子も上の子も、そして保護者も笑顔になれる6つの工夫をご紹介します。
兄弟学習トラブル、なぜ起きる?
まず知っておきたいのは、「なぜトラブルが起きるのか?」ということ。
多くの場合、下の子は「お兄ちゃん、お姉ちゃんばっかり!」「ママ(パパ)を取られた!」という気持ちでいっぱいです。特にまだ言葉がうまく使えない年齢の子は、「かまってほしい」という気持ちを“邪魔”という行動でしか表現できません。
一方、上の子は「ちゃんとやろうとしているのに…!」という思いでいっぱい。集中できずにストレスがたまり、下の子に強くあたってしまうこともあります。
親の手が2本しかない中で、この2つの欲求に同時に応えるのは無理があります。だからこそ、時間や空間の使い方に「ちょっとした仕掛け」が必要なのです。
工夫①:静かに遊べる“お助けアイテム”を用意しよう
同じ部屋で過ごしつつ、上の子の学習を邪魔しないために、下の子には「静かに集中できる遊び」を用意してあげましょう。
おすすめは以下のようなグッズ
- 折り紙やぬりえ(キャラクターものが人気)
- シールブックや迷路の本(100均の「知育シリーズ」など)
- マグネットブックやパズル(100ピース以下)
- スクラッチアート(削って絵が出てくる)
これらはすべて、子どもが一人で操作でき、かつ「手を使って集中する」タイプの遊びです。目新しいものを入れ替えながら使えるように、「おたのしみBOX」を用意しておくとより効果的です。
「静かに遊べたらスタンプ1個!」など、ごほうび制度を導入しても良いでしょう。
知育玩具のご紹介
【日本サブスク大賞2024日本ネット経済新聞賞受賞】
Cha Cha Chaは0歳〜6歳までのお子様に向けた 知育玩具のサブスクリプションサービスです。
工夫②:下の子も「お勉強ごっこ」で満足!
「お兄ちゃん、お姉ちゃんばっかりズルい!」という気持ちを抑えるには、下の子にも「勉強している気分」を味わわせてあげるのが効果的です。
例
- 線なぞりや点つなぎのプリント(「ぷりんときっず」など無料サイトあり)
- ひらがな・数字ドリル(学研・くもん出版など市販も多数)
- 幼児向けのお絵かきワークや知育シール台紙
年齢に合った内容を選び、同じタイミングで「机に座る」体験をさせましょう。おそろいの文房具を用意するとテンションも上がります。
「ママ先生役」「パパ助手役」など、ちょっとしたごっこ遊びとして展開すると、子どもたちの取り組みがぐっと楽しいものになります。

我が家では同じダイニングテーブルの端と端で、上の子に手が届かないように下の子を遊ばせていました!
無料プリントのご紹介はこちら(幼児知育もあります)
工夫③:「ご飯やおやつ中」が最大のチャンス!
実は、下の子が最も静かに集中している時間、それが「ご飯やおやつを食べているとき」です。
たとえば、15時のおやつタイム。おせんべいや果物など、ある程度時間がかかるものを選んで出せば、下の子はおとなしく座って食べてくれます。
そのタイミングを狙って、上の子の「集中が必要な学習(漢字、計算ドリルなど)」を行うと非常にスムーズです。親がそばにいてフォローすることもできるので、一石二鳥。
朝ごはんや夕食の支度前にも同様の方法が使えます。
工夫④:「見守り学習」で親もラクに
「ずっとつきっきりでいないと勉強が進まない」と思っていませんか?
実は、子どもが自主的に取り組むには「ちょっと離れて見守る」ほうが効果的な場合もあります。
タイマーを使って5〜10分ごとの「チェックイン方式」を試してみましょう。
1.「次のページまでやってみよう」
2. タイマーをセットして離れる
3. 音が鳴ったら確認に戻る
4. 丸つけや簡単なアドバイスだけ行う
この方法なら、下の子と遊ぶ時間や家事との両立も可能。上の子は「自分でやった!」という達成感も得られるため、家庭学習へのモチベーションも上がります。

下の子の食事に目が行き届き、上の子の勉強も見てあげられるのでおススメです。
工夫⑤:「順番タイム」で親も子もスムーズに
兄弟同時に満足させるのが難しいときは、時間を区切って「順番制」にしましょう。
たとえば:
- 15:00〜15:20 上の子の学習タイム(下の子は静か遊び)
- 15:20〜15:40 下の子との遊びタイム(上の子は自習または休憩)
「時間が来たらちゃんと見てもらえる」と下の子が分かっていれば、無理に割り込もうとしなくなります。保護者も“集中タイム”と“子どもタイム”を明確に切り替えられるので、気持ちに余裕が生まれます。
工夫⑥:テーブルに“境界線”を作るだけでも効果あり
一緒のテーブルで過ごすなら、「空間を分ける」工夫をしましょう。物理的にスペースを分けると、トラブルはぐっと減ります。
ダイニングテーブルやローテーブルにマスキングテープで境界線を引き、
- こちらはお兄ちゃんやお姉ちゃんの学習ゾーン
- こちらは○○ちゃんのお楽しみゾーン
と伝えましょう。年齢が低い子でも、視覚的に理解しやすくなります。
必要に応じて、つい立てやボードで簡易的な仕切りを作ると、さらに集中しやすい環境になります。動範囲が自然と制限されます。パーテーションやつい立てを使えば、視覚的にも集中しやすくなります。
完璧を求めず、できる工夫から
いかがでしたか?今回は、『下の子がいても集中できる!きょうだい育児と家庭学習を両立する6つの工夫』をご紹介しました。
家庭学習と兄弟育児を完璧に両立させるのは至難の業です。うまくいかない日があっても当然。「今日は少し静かにできた」「昨日より笑顔が増えた」と、成長のきっかけを見つける姿勢が大切です。
兄弟・姉妹がいても、家庭学習の時間を大切にできる。そんなあたたかい時間を少しずつ増やしていきましょう。保護者自身の心の余裕も、子どもたちの学びを支える大切な土台です。