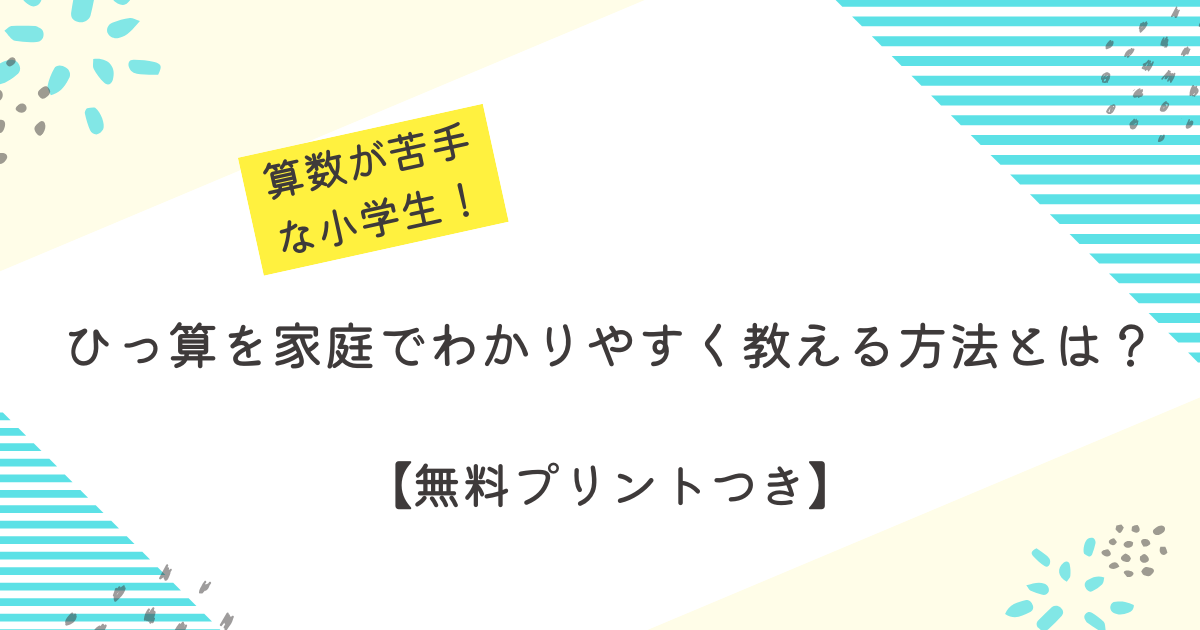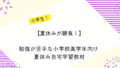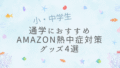こんにちは。学びのインフォです。
小学生のママさんによく聞かれるのは、算数の『ひっ算』についてです。子どもが理解していないようだけれど、教えることが難しい。どうしたらうまく説明してあげられるのか?
今回はそんなママさんたちのお悩みのお手伝いになればと思い、『ひっ算の攻略!』をお届けします。
ひっ算に苦手意識がある理由とは?
まず、子どもがひっ算でつまずく主な原因は次のようなものだと考えています。
- 数の大きさの感覚があいまい(位取りが理解できていない)
- 繰り上がり・繰り下がりの意味があやふや
- 計算手順を丸暗記していて、理由を理解していない
- 書き方のルールが定着していない(数字のずれ、位のズレ)
これらをふまえた上で、教え方の工夫・教材をお届けしようと思いました。
教えるときの3つのポイント
「位」を徹底的に意識させる
ひっ算のカギは「位どおりに数字を書く」こと。
数字をマス目にそろえて書くことで、繰り上がり・繰り下がりを視覚的に理解しやすくなります。
▼工夫:
- 方眼ノートをつかってみましょう
- 消しゴムで消させずに、ミスした場所を赤で丸つけして振り返らせる
- 「一の位」「十の位」「百の位」と声に出して確認しながら計算する
「操作」の意味を図や具体物で見せる
筆算は手順を覚えることがゴールではなく、「なぜこの操作をするのか」を理解させることが重要です。
▼工夫:
- 100玉そろばんやブロック(百均でもOK)を使って、繰り上がり・繰り下がりを再現
- 絵で見せるプリントや動画教材を活用する
- 「10を借りる」「10を渡す」動きを実演して見せる
▽具体例:
繰り上がりの再現(例:28+7=?)
使用する道具:
- ブロック(10個で色を変えるか束ねられるタイプがおすすめ)
- または「100円玉そろばん」「10玉そろばん」など、10個単位でまとまる視覚素材
手順①「28」をブロックで表現
- 10のまとまり(10個)ブロック ×2=20
- 1個ブロック ×8=8
👉 ブロック合計28個
手順②そこに「7」を追加
- 1個ブロックをさらに7個追加
👉 今、1の位は「8+7=15」ブロックある状態
手順③10個のブロックをまとめて10の位に繰り上げる
- 「15」は「10+5」と考えて、10個のブロックを1本の10のブロックにする
- 残りの5個は1の位に残す
手順④最終的に:10の位→3本(20+10)、1の位→5個
👉 答え:35
繰り下がりの再現(例:41−6=?)
使用する道具:
- 同様に10個単位でまとまるブロックや100円玉そろばん
手順①「41」をブロックで表現
- 10のブロック4本(=40)
- 1のブロック1個
手順②そこから「6」を引きたいが…
- 1のブロックが1つしかないので、6は引けない!
手順③そこで10のブロック1本を“1のブロック10個”に崩す(繰り下がり)
- 10の位:4→3本になる
- 1の位:1+10=11個になる
手順④11から6を引く=5個残る
👉答えは:35

子どもに声かけするときは・・・
「1のブロックがたりないね。じゃあ10のを1本、こわしてみようか」
「10の1本って、1のブロック10個になるんだよ」
「これが“くり下がり”!」
なんてしてみるといいですね。
「説明させる・考えさせる」を意識
- 「なんでここを1繰り上げたの?」など、自分の言葉で説明させると理解が定着
- あえて間違った例を見せて「どこが違う?」と考えさせる
- 「正解したか」より「考え方を表現できたか」をほめましょう
おすすめの無料プリント&ネット教材
ちびむすドリル
- 小1〜小6まで学年・単元別にプリントが豊富
- ひっ算専用の「繰り上がりあり」「繰り下がりあり」プリントが段階的に揃っていて◎
- マス目つきなので、位を意識させやすい

「つまずいた問題」と同じ形式のプリントを探して復習するのに最適です
ぷりんときっず
- とにかく見やすい・取り組みやすいデザイン
- 文字や数字が大きく、数字の書き方が雑なお子さんにもおすすめ
- 計算ドリルがシンプルで継続しやすい

「今日は1枚だけ!」と習慣化に向いた教材です
NHK for School「さんすう犬ワン」
- 小学生向けの学習アニメシリーズ
- ひっ算の仕組みや、繰り上がり・繰り下がりを楽しく・視覚的に理解
- 動画+クイズ形式で、飽きずに学べる

「動画でわかった→紙で練習する」流れが効果的です
保護者が心がけたい3つのこと
| 心がけ | 解説 |
|---|---|
| ❶ 間違えても責めない | 「どう考えたのか」を一緒に探る姿勢が◎ |
| ❷ 毎日短時間でOK | 「1日1枚」など小さな積み重ねが自信に |
| ❸ 正解よりプロセスを重視 | 「説明できるかどうか」が理解のカギ |

言われなくてもご理解いただいていると思いますが、忙しいママさんたちだからこそ、この心がけ1つでお子様の「分かった!」という笑顔が見られると嬉しいです!
おまけ:遊び感覚で身につく!おうちでできるアイデア
「お店屋さんごっこ」でひっ算を実感!
- 手作りのレジ&おもちゃのお金を使って、買い物ごっこ
- 合計金額やおつりをひっ算で計算(たし算・ひき算・かけ算の応用)

「実生活で使う」ことで、計算の意味がぐんとリアルになります
「まちがいさがしプリント」で理解度チェック!
- あえて間違えた計算式を提示
- 「どこが間違ってるかな?」と一緒に考える

「どう直すか」まで自分で言えれば、完璧です!
お店屋さんごっこ・まちがいさがしプリント
私個人で使用したものを掲載しておきますので、よければご自由にお使い下さい。
ひっ算の“できた!”が聞きたいですね
いかがでしたか?今回は、『ひっ算を家庭でわかりやすく教える方法とは?』をご紹介しました。
ひっ算は、大人にとっては「簡単」に見えても、子どもにとっては見えないルールが多くて戸惑いやすい単元です。
でも、ブロックや100円玉、買い物ごっこなど、目に見える形で体験させてあげることで、少しずつ「そういうことか!」という理解が生まれます。
大切なのは、一度でわかることを求めすぎないこと。
「何度も間違える」「うまくできない」そんなときこそ、子どもの心はぐんと育っています。
家庭だからこそできることがあります。
「間違ってもいいよ」「いっしょに考えよう」――その一言が、子どもにとって何よりの安心材料です。
今回ご紹介した教材や教え方の工夫が、ご家庭での「楽しい学び」の時間につながりお役に立てれば嬉しいです。