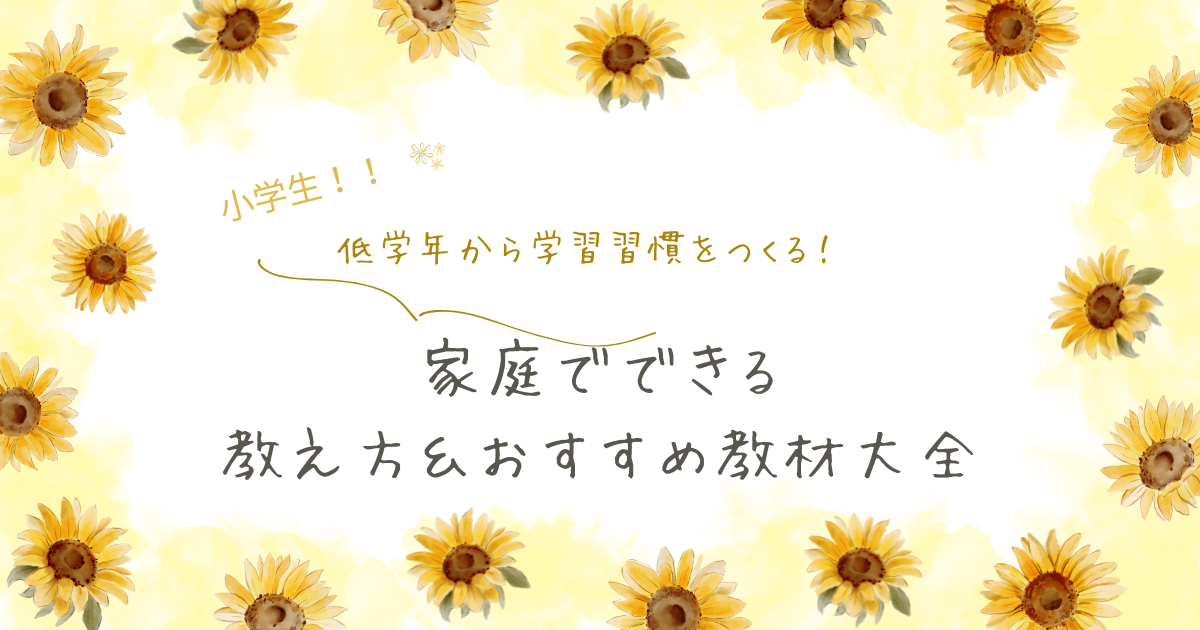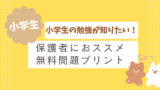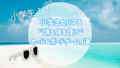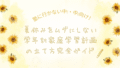こんにちは。学びのインフォです。
「小学校低学年のうちは、遊びが一番!」
確かにそれは大切なことです。しかし、だからといって“学習習慣づくり”を後回しにしてしまうと、後々になって「机に向かえない」「勉強が苦手」という壁にぶつかりやすくなります。
低学年のうちに学ぶ内容は、すべての教科の“土台”になります。特に家庭でのサポートが大きな力になるこの時期こそ、親子で一緒に学ぶ楽しさを育むチャンスになります。
今回は、算数をはじめとする主要教科のつまずきポイントや教え方のコツ、おすすめ教材・YouTubeチャンネルなどを紹介します。今日から家庭でできる工夫を、ぜひ取り入れてみてください。
算数のつまずきポイントと教え方
よくあるつまずき:「くり上がり・くり下がり」「文章題」「時計・図形」
小学校低学年の算数で特につまずきやすいのは、以下の3つです。
- くり上がり・くり下がりのある計算
- 文章題
- 時計や図形の理解
それぞれについて、教え方のコツを紹介します。
くり上がり・くり下がり:100玉そろばんで視覚化!
教え方のコツ:
- 100玉そろばんを使い、10のかたまりがいくつあるかを見て数える。
- おはじきやブロック、お菓子などを使って「10個で1セットになる」感覚を体験させる。
- 筆算に入る前に「具体物での操作」→「絵」→「数字」の順にステップアップ。
- まずは「繰り上がらない」計算を十分に練習し、次に「くり上がり」へ。
おすすめ教材・YouTube:
- 『100玉そろばんで計算名人!』(学研)
- YouTube「かずのがくしゅうチャンネル」
└ 動画でくり上がり・くり下がりの動きを視覚的に理解できます。
文章題:絵でかく&読んであげる
文章題では「問題文が理解できない」ことが最大のハードルです。
教え方のコツ:
- 問題を読んであげて、絵にしたり「誰が」「何を」「いくつ」を分けて考える。
- 登場人物に名前をつけるなど、イメージしやすい工夫をする。
- 絵に描いたり、おはじきなどを使って「状況」を見える化。
- 「何をたずねているか?」を声に出して確認する。
おすすめ教材・YouTube:
- 『文章題にぐーんと強くなる』(くもん出版)
- YouTube「とある男が授業をしてみた(低学年編)」
└ イラスト付きで文章題を解説してくれるので理解しやすいです。
時計・図形:実物やアプリで感覚的に学ぶ
アナログ時計や図形の認識は、言葉で説明しても伝わりづらいもの。
教え方のコツ:
- 実物の時計で一緒に針を動かして学ぶ。
- カタチ遊びや折り紙、ブロックで図形を触って体験する。
- 家にある物で図形を見える化してあげる。
おすすめ教材・アプリ:
- 『とけいのほん①②』(福音館書店)
- YouTube:NHK for School「さんすう犬ワン」、KUMONの公式チャンネル
英語:低学年のうちに始めるならコレ!
小学校での英語教育は本格化していますが、低学年では「無理なく」「楽しく」「音から」が基本です。
学習の進め方:
- まずは「聞く・まねする」から。英語の歌や絵本を活用。
- 発音は“間違っていてもOK”。親子で一緒にリズムに乗ることが大切。
- 無理に文字を書かせない。「耳→口→目→手」の順が自然。
教えるコツ:
- 親が楽しむ姿を見せると、子どもも真似します。
- 朝や夕方の決まった時間に短時間(5分〜10分)取り入れる。
おすすめ教材・YouTube:
- 『Goomies English for KIDS DVD』:英語に触れる時間として「ながらDVD」として流し、気になるフレーズを一緒にリピート。また、フレーズを真似することでスピーキング能力も自然に育ちます。
- YouTube「Super Simple Songs」:英語の歌で自然に発音が身につきます。

発音や文法の正しさよりも、親子で「楽しいね!」を共有する姿勢が大事です。
国語:読解力は家庭で伸びる
低学年の国語は、ただ文字を読めるようになるだけでなく、「意味を理解する力」「言葉を使って表現する力」が重要です。
家庭でできること:
音読の習慣をつける
- 毎日の音読を習慣に。親が聞いてあげるだけでOK。
語彙を増やす会話・遊び
- ことわざや慣用句を一緒に楽しむ(カードゲームなど)
感想・意見を言葉にする練習
- 絵本やアニメのあとに「どう思った?」「好きな場面はどこ?」と質問する。
- 最初は口頭でOK。慣れたら短く書いてみるのも◎
おすすめ教材・YouTube:
- 『はじめての小学生ことばパズル クロスワード 1・2年生』(学研プラス)
- 『考える力がつく 国語なぞペー 小学1年~3年生』(草思社)
- YouTube「NHK for School“国語”」シリーズ:小学生向けに分かりやすく解説。
理科・社会:生活とリンクさせて「好き」を育てる
理科や社会は、低学年では「生活科」として扱われます。実際の生活に深く結びついており、「なぜ?」「どうして?」を一緒に楽しむことが学びの第一歩です。
学び方の工夫:
- 花や虫の観察、家庭菜園など身近な体験を重ねる。
- 地図を見ながらおでかけプランを立てる。
- お手伝いを通じて「社会のしくみ」にふれさせる。
おすすめ教材・YouTube:
- 『学研の図鑑LIVE』シリーズ(昆虫・恐竜・人体など)
- YouTube「しましまとらのしまじろう:しぜんチャンネル」
- NHK for School「ふしぎエンドレス」
家庭学習の習慣化:1日15分ルールでOK
どの教科にも共通するのが「毎日少しずつ」が基本であること。
長時間やる必要はありません。むしろ低学年のうちは、短くても「毎日」やることが大事です。
習慣化のためのコツ:
- 時間を固定する(例:夕食前の15分)
- 声かけはシンプルに:「今日もあの計算一緒にやろうか」
- 終わったらたくさん褒める!(内容より姿勢を評価)
- “選ばせる”ことを習慣にする:「今日は国語と英語どっちにする?」

最初は親が横についてサポートをしてあげて下さい。徐々に子どもが「自分でやる」方向に移行していくのが理想です。
子どもと一緒に「楽しく学ぶ」ことが成功のカギ
いかがでしたか?今回は『低学年から学習習慣をつくる!家庭でできる教え方&おすすめ教材大全』をご紹介しました。
小学校低学年の学びは、家庭での関わり方次第でグンと伸びます。
勉強に対して前向きな気持ちを持たせるためには、親の接し方がとても大切です。
「勉強を教えるのは自信がない…」そんな声をよく耳にしますが、完璧な指導は必要ありません。
「教える」のではなく、「一緒に楽しむ」。この意識を持つことで、子どもの“学ぶ力”は自然と育っていきます。
たった1日15分でも、毎日の積み重ねは大きな差になります。低学年の今こそ、家庭で「学ぶって楽しい!」という経験をたくさんさせてあげましょう。
この記事がみなさんのお役に立てれば嬉しいです。