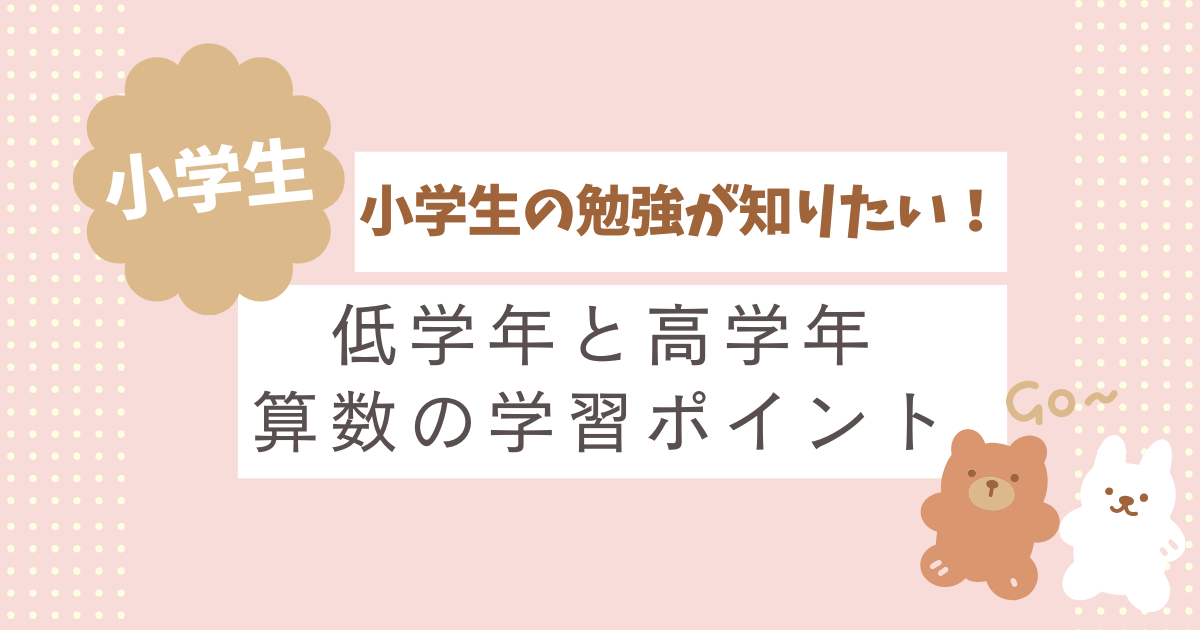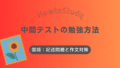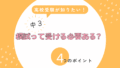こんにちは。学びのインフォです。
算数という教科は、積み重ねの知識や理解から成り立つ教科だと言われています。では小学生のうちにやっておきたい算数の勉強とはどういったことなのでしょうか。今回は小学生の算数についてお話していきたいと思います。
算数は積み重ねと言われる理由
小学校に入学すると、数のかぞえ方から足し算や引き算、時計の読み方や時間の単位などを学びます。一番最初のつまづきポイントは、2年生から始まるかけ算です。
かけ算につまづき、わり算につまづいてしまうと、その先の計算全てに影響が出てきてしまいます。かけ算を覚える時は出来るだけ一緒にやってあげると良いでしょう。
また3年生になると、少数や分数といった2つ目のつまづきポイントに遭遇します。かけ算やわり算もそうですが、分数や少数も今後算数や数学を学習していくうえで確実に必要な基礎知識となってくるので、きちんと理解して次の学習に進めていきたいポイントです。
1年生のうちから、図形に関する学習もしていきます。図形も学年が上がるにつれて基礎がしっかり理解できていないと中学生になってから苦労するでしょう。
このように、算数はその先の数学に繋がる積み重ねの科目と言われているのです。
小学生のうちに確実に理解しておきたい算数
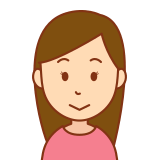
小学生はどんなことを気をつけておけば良いですか?
このような質問をよくされます。
小学生のうちに確実に出来るようにしておきたいのは四則演算です。
足す(+)、引く(-)、掛ける(×)、割る(÷)
全部が混ざっている計算式では、掛け算と割り算を先に計算するルールやカッコの中を先に計算するなど算数のルールを理解して覚えていることが大切です。
少し学年が上がると、分数や少数に加えてさまざまな単位を覚えたり、単位変換を学習します。どの単元もつまづいてしまいがちなポイントです。
これらそれぞれの単元で、苦手意識を持ってしまうと中学生になってからも苦労をしてしまいます。出来るだけその単元ごとに苦手部分を無くして次の単元に向かうようにしましょう。
身近なもので一緒に楽しく学ぶ算数(全学年共通)
お子様が算数でつまづいているとき、算数を楽しいと思える方法の1つとして身近な物を使って楽しく一緒に算数を学ぶことをおススメします。
例えば分数が苦手な場合、我が家ではリンゴを切って教えていました。実際に半分に切ったり1/4に切ったりすることで、目で見てイメージしながら理解することが出来ます。

実際に目で見てイメージしたあとは、美味しく食べる!
案外子供も喜んでくれますよ!
図形も同じです。世の中には正方形も直方体も少し探せば家の中にあるものです。展開図を教える時は、ティッシュや薬の箱を解体してリアルでイメージ出来るように実物を見せていました。
掛け算や割り算を具体的にイメージしてもらう為に、飴をたくさん用意して実際の家族の人数で振り分けてみたりもしました。
そんなことをしている時間が無いというご家庭も多いと思います。そしてこれは例の1つです。実際にやって見せなくても、お子様との会話の中で算数的要素を混ぜることも、コミュニケーションの1つとして行えば楽しい時間となるかもしれません。
小学生のお子様にとって、両親とのコミュニケーションの時間というのは嬉しく楽しい時間です。我が家では習い事などの車移動の時間に、クイズ形式とかで算数の問題出したりしていました。

なつかしいな~
低学年(1年~3年)におススメの学習ポイント
学習時間は短時間で
低学年のうちは集中力も短く、長時間の勉強というのは勉強嫌いのきっかけにもなりかねません。
低学年のうちはむしろ、元気よくお友達と遊ぶ!というほうが子供らしくて良いでしょう。学習習慣を小さいうちから身につけさせたいと思う方も多いですよね。低学年向けの算数のおススメ学習ポイント1つ目は、短時間で出来る『1日1枚の計算プリント』です。
これならば、お子様も短時間で集中して望めます。また、「できた!」という達成感も得られるでしょう。そして毎日5分でも机に向かう習慣が身に付き、計算力も養われる。

プリントで間違えたところを確認すれば、「〇の段の掛け算が苦手なのかな?」といった細かいところにも気付けるきっかけにもなりますよ。
統計やカレンダーを使おう
低学年向け算数のおススメ学習ポイント2つ目は、『時計やカレンダーを使おう』です。日常生活で時計を読ませたり、1時間後・30分後を考えさせることで後の算数学習に役立てることが出来ます。
日常会話の中で今日の日付や曜日を確認させることで、カレンダーの読み方を教えたり、日数の計算をさせることで高学年になったら出てくることが増える文章題への備えが出来ます。
長期休暇の学習ポイント
長期休暇の算数の学習ポイントは、計算プリントを十マス計算から百マス計算まで学年に応じてチャレンジして計算力を向上させたり、小学生向けの算数アプリを利用してゲーム感覚で楽しく算数に触れるぐらいが良いでしょう。

一緒に買い物へ出かけて、「これとこれを合わせるといくら?」と質問するのも良いですね。
高学年(4年~6年)におススメの学習ポイント
学習時間は学年×10分を目安に始めてみましょう
高学年になるにつれて勉強も難しくなってきます。3年生までの算数で苦手なところが出てきているお子さんもいることでしょう。やはり学年が上がるにつれて、最低限の学習時間は確保したいところです。
学習時間の目標は学年×10分ですが、毎日絶対に確保という訳ではなく、平日に取れなかった分はお休みの日に少し回すでも構わないです。子供がムリなく続けられる学習習慣を身に着けることが大切です。
文章題は読み解く力をつける
今後増えていく文章題は算数に苦手意識を持つきっかけにもなりやすいところです。学習のポイントとしては、図を書いて整理しながら解く習慣をつけたり、問題文の意味を正しく理解する練習をすることが大切です。
計算力を身につけましょう
算数の勉強に不可欠なものが計算力です。毎日短時間の計算練習(10~15分)をおススメします。計算ミスを減らすために途中式をしっかり書くことが、計算力向上のポイントになります。
途中式を書いておけば、自分がどの時点で計算ミスをしているのか、丸付けをした時に見返すことが出来るからです。

お子様が丸付けを自分でした時に、どこで計算ミスをしているのかをちゃんと確認するように促しましょう。
長期休暇の学習ポイント
長期休暇の算数の学習ポイントは、苦手単元を復習して基礎を固めることです。自分が苦手な単元は、YouTubeなどの解説動画を参考にみたり、市販の問題集などを活用するのもおススメです。
毎日最低限『学年×10分の勉強時間』を確保し、長期休暇中の学習スケジュールを大雑把でも構わないのでたてておくと、「気がついたら休みが終わりに近づいている!」ということも無くなるでしょう。

旅行や買い物の際に「速さ」「距離」「割引計算」などを会話の中に入れることで、日常で使う身近な算数としておススメです。
まとめ
いかがでしたか?今回は、『小学校低学年と高学年の算数学習ポイント』を5つのポイントでご紹介しました。
このブログでは実際に質問されることの多いものを中心に取り上げています。初めてのお子様だと学習方法が不安だったりしますし、ご兄弟がいてもお子様の性格の差などから不安になることが違ったりしますよね。
お役に立てることがあれば嬉しいです。