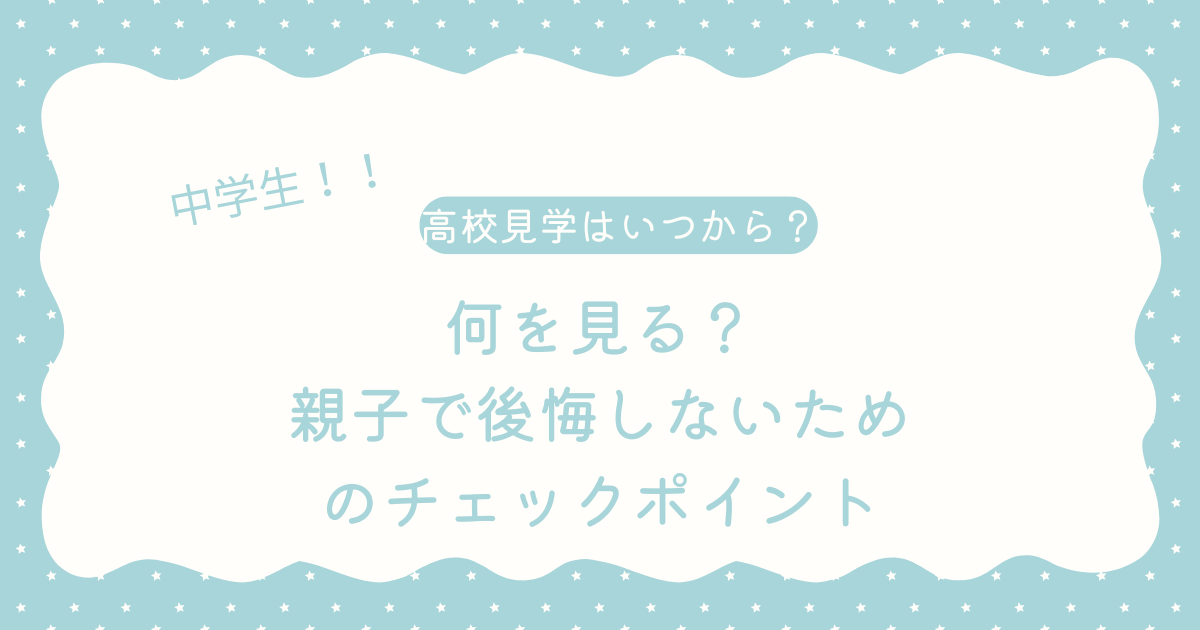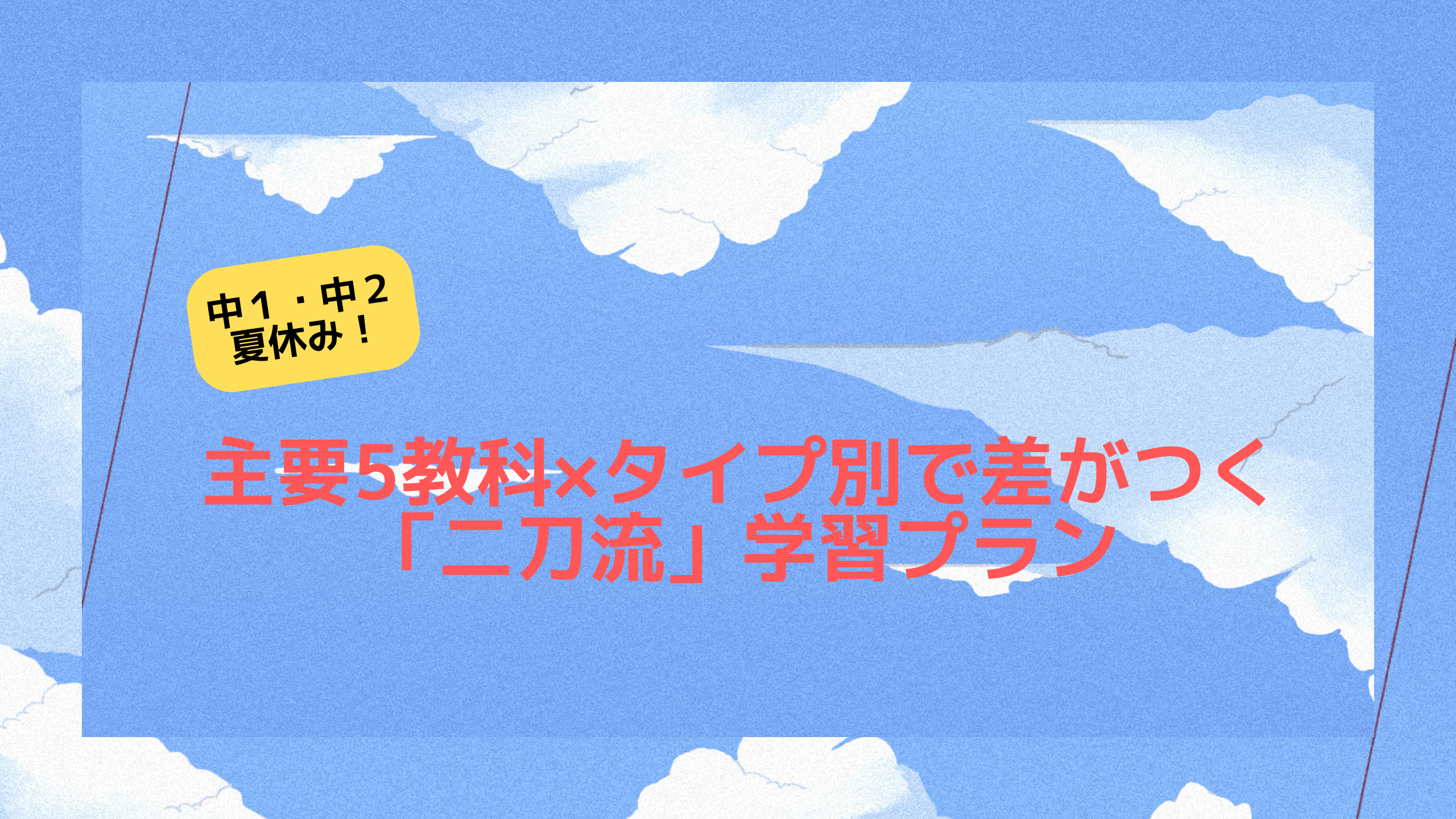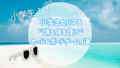こんにちは。学びのインフォです。
夏休みが近づいてきて、学校説明会や夏の部活動体験会などが本格的に開催されますよね。高校受験は、子どもにとって人生の大きな分岐点。そして保護者にとっても、「どんな高校を選べばいいのか」「本当にこの学校で大丈夫か」と悩む時期です。特に最近では、学校ごとの特色や雰囲気、進学実績、生活環境の違いが大きく、入学後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔する声も少なくありません。
だからこそ大切なのが、高校説明会や文化祭などの「リアルな学校の姿」にふれること。パンフレットや偏差値だけでは見えない“本当の高校生活”を、自分の目で確かめることが、後悔のない進路選びにつながります。
今回は
- 高校見学はいつから始めるべきか?
- 説明会や文化祭でチェックすべきポイントは?
- 親と子、それぞれが見るべき視点の違いとは?
などを分かりやすく解説していきます。
「高校見学はまだ先でいいかな」と感じている中学生や保護者の方にこそ読んでいただきたい内容です。この記事を通して、親子で納得のいく高校選びができるよう、今からできる準備を始めましょう。
高校見学・説明会はいつから行くのがベスト?【学年別ガイド】
高校見学や説明会は、なるべく早めの行動がカギになります。以下に学年別の理想的なスケジュールを紹介します。
【中学1年生】
→まだ高校選びを本格的に考える段階ではありませんが、きょうだいや友達のつきそいで文化祭などに行ってみるのは◎。高校へのイメージづくりができます。
【中学2年生】
→夏〜秋にかけて、本格的に文化祭や公開授業などのイベントが開催されます。志望校の選択肢を広げるためにも、この時期に「最低2〜3校」は見学しておきたいところ。見学=受験確定ではないので、気になる学校はどんどん行ってOKです。
【中学3年生】
→説明会や個別相談会が本格化。秋には私立・公立ともに進路相談や願書準備が始まるため、夏までに見学を終えるのが理想。9月以降は志望校を選定するつもりで本腰を入れて参加したり、「志望校の最終確認」の場としての説明会参加を想定しましょう。

*学校によっては、中3生のみの参加と限定されている説明会もあるのでホームページなどで確認をしましょう。
学校説明会でチェックすべき7つのポイント
学校説明会では、パンフレットだけではわからない情報が得られます。以下の7つのチェックポイントを意識しましょう。
進学実績や就職実績
生徒がどのような進路を選び、実際にどんな大学や専門学校、就職先に進んでいるのかを確認しましょう。特に公立高校では「指定校推薦の枠がどれくらいあるか」「国公立大への進学サポートがあるか」などがポイントです。
→【チェック質問例】
「近年の大学合格者数は?」
「指定校推薦はどのような条件で出される?」
「卒業生の就職支援はあるか?」
授業や補習の内容・方針
授業スピードや補習体制は学校ごとに大きく異なります。「自学自習重視」なのか、「先生が丁寧に教えるタイプ」なのかも確認しましょう。
→【チェック質問例】
「テスト前の補習や対策授業はありますか?」
「学力別クラス分けはされていますか?」
「課題は多い方ですか?」
校則や生活指導の方針
「自由な校風」と聞いても、何がOKで何がNGかは校内のルール次第。スマホの持ち込み、髪型、アルバイトなど、気になる項目を事前にチェックしましょう。
→【チェック質問例】
「スマホは校内で使用可能ですか?」
「アルバイトは許可されていますか?」
「生活指導はどのように行っていますか?」
通学の利便性と安全性
自宅からの通学時間・経路はもちろん、登下校時の治安や混雑状況も含めて確認しましょう。雨の日や冬場の様子も想像しておくと安心です。
→【チェック質問例】
「最寄り駅から学校までの道のりは安全ですか?」
「自転車通学は可能ですか?」
「交通機関が止まった時の対応は?」

バス通学は遅延の対象外の場合もありますので要注意です!
学校の雰囲気と先生の印象
説明会や見学中に感じる「雰囲気」は非常に重要です。生徒の表情や態度、先生方の話し方や距離感など、肌で感じる印象を大切に。
→【チェック方法】
・先生の話し方に威圧感がないか
・生徒同士の会話に笑顔があるか
・学校案内役の生徒が自信を持って話しているか

生徒が学校案内をしている時は、実際に学校生活がどうなのかを聞けるチャンスです!
ICTや施設の充実度
ICT(情報通信技術)の活用状況や、校舎・教室の設備、図書館や自習室の充実度も確認ポイントです。学びの環境が整っているかどうかを見ておきましょう。
→【チェック質問例】
「タブレット端末は全員配布ですか?」
「Wi-Fiは自由に使えますか?」
「放課後、自習スペースは開放されていますか?」

公立高校でもタブレットを自己負担で購入するケースもあります。チェックしておきたいポイントですね。
入試制度と選抜方法
推薦入試、一般入試、単願・併願の制度など、入試の仕組みも学校ごとに違います。出願条件や必要な書類、選考の基準をしっかり確認しておくと安心です。
→【チェック質問例】
「推薦入試で必要な内申点は?」
「面接の内容はどのようなものか?」
「入試の得点配分や合格基準は公開されていますか?」
これら7つを踏まえ、親子で質問リストを準備してから説明会に臨むと、情報の取りこぼしがなく、比較しやすくなります。

トイレがキレイに清掃されている学校は、比較的その他もキレイな傾向にあるので意外なチェックポイントです。
文化祭・体育祭などのイベントで「その高校らしさ」を体感しよう
説明会では見えにくい「リアルな学校生活」を知るには、文化祭や体育祭などのイベントが最適です。
● 生徒の雰囲気が見える
● 先生と生徒の距離感がわかる
● 部活動の活気を感じる
こうした学校行事は、「楽しそう」「自分にもできそう」という直感的な感覚が得られるチャンスです。説明会とセットで参加できるとベストです。

学校のHPや資料では素敵に見えた学校でも、実際に文化祭などに行くと生徒が全然楽しそうではなく、行事仕事として参加している様子が伺えることもあります。自分の目で見て感じることは大切です。
親と子で「見るポイント」は違う!両方の視点を持とう
高校見学や説明会では、保護者と生徒で気になるポイントが違うのが自然です。だからこそ、両方の視点を持ち寄って話し合うことが、後悔しない学校選びにつながります。
【保護者が重視しがちなポイント】
- 進学実績や学費などの経済的な面
- 通学手段の安全性
- 先生の話し方や説明の丁寧さ
- 校則や生活指導の厳しさ
- 卒業後の進路・サポート体制
【子どもが気にするポイント】
- 学校の雰囲気(楽しそうか・合いそうか)
- 制服や校舎のデザイン
- 部活動の活発さ
- 友達が行きたいと思っているか
- 校則が厳しすぎないかどうか
保護者が「この学校はいい!」と思っても、子どもが「通いたくない」と感じてしまっては本末転倒。逆に、子どもが「楽しそう」と思っても、保護者が不安を感じていると送り出すのも心配になります。
【ワンポイントアドバイス】
説明会では、親子で「質問リスト」をあらかじめ分担しておくのもおすすめです。
例:
- 子ども→部活動、制服、校則、学校行事など
- 保護者→学費、進学実績、補習、通学手段など
あとで家に帰ってから、「お互い何を感じたか」を話す時間をつくりましょう。親子で意見を出し合うことで、より納得のいく選択ができるようになります。
「偏差値」だけで選ばない!学校選びで失敗しないための心構え
高校を選ぶときに、偏差値だけで判断してしまうご家庭は少なくありません。もちろん、受験において偏差値は重要な目安です。しかし、それだけでは見えない「本当に合う学校かどうか」は、実際に見て・感じて・調べて初めてわかります。
たとえば、同じくらいの偏差値でも、
- 自由な校風で生徒の自主性を尊重する学校
- きめ細かいサポートで学力を引き上げる進学校
- 部活動に力を入れている文武両道の学校
など、校風は大きく異なります。
「偏差値が足りているからここでいいや」ではなく、
「ここに通いたいから、がんばって偏差値を上げよう!」
という志望動機がある方が、受験勉強のモチベーションも長続きします。

高校を選ぶ時に、その高校が文系が強いか理系が強いかにもよって選択が変わることがあります。お子様が将来進みたい道がある場合は、その方向性に沿える学校なのか。将来がまだみえない場合は、その高校へ進むとどんな方向へ進むことが出来るのかを保護者の方がお子様の性格なども踏まえて選択するサポートをしてあげて下さい。
説明会・見学に行った後は「振り返り」をしよう
高校見学や説明会に参加したら、行きっぱなしにせず、記録を残すことが大切です。学校ごとに印象が混ざってしまうことも多いため、比較する際に役立ちます。
【親子で活用できる「振り返りメモ」の例】
- 学校名/訪問日/イベント名
- 校舎や施設の印象
- 説明の内容(進学、生活、学費など)
- 生徒や先生の印象
- 子ども・保護者それぞれの感想
- 良かった点・気になった点
また、訪問後の「気持ちの変化」もメモしておくと、時間が経ってからも正確に思い出すことができます。
【PDFやアプリを使って記録するのも◎】
最近では、高校見学の振り返りシートをPDFやノートアプリで管理する家庭も増えています。自分なりにテンプレートを用意しておくと便利です。
こんな高校イベントにも注目!「説明会・文化祭」以外に見るべき機会とは?
高校選びでよく知られているのは、「説明会」や「文化祭」ですが、実はそれ以外にも貴重な見学機会があります。
【授業公開日】
実際の授業の様子が見られる貴重なチャンスです。生徒の集中度や先生の指導スタイルがそのまま分かります。
【部活動体験会】
中学生を対象とした体験イベントを開催している高校もあります。雰囲気だけでなく、実際の活動量や指導の雰囲気が感じ取れるため、入学後のイメージを具体化できます。
【個別相談会】
説明会で聞きそびれた質問や、成績・学力に関する具体的な相談ができる場です。成績の見通しや、入試対策のヒントも得られるため、受験直前には特におすすめです。
【オンライン説明会・動画配信】
遠方の学校やスケジュールが合わない場合には、学校公式サイトやYouTubeチャンネルなどで配信されている動画コンテンツも参考になります。ただし、編集されているので「良いところだけを見せている可能性がある」ことも意識して見ましょう。
見学で「感じた違和感」は、スルーしないで!
保護者・生徒ともに、「なんか雰囲気が合わない気がする」「先生の話し方が少し威圧的だった」など、小さな違和感を覚えることがあります。
こうした感覚は、案外的中するものです。
大人が職場見学に行って「この会社は合わない」と直感的に感じるのと同じで、学校の空気感も、説明では伝わらない“肌感覚”があります。
そのためにも、1校だけでなく、複数の高校を比較することがとても大切です。比較するからこそ、自分たちに合った学校が浮き彫りになります。

我が家では上履きの有、無しも気になるポイントでした(笑)
親子で一緒に考える「志望校の優先順位リスト」を作ろう
高校選びにおいて、すべての条件を満たす理想の学校に出会えることは稀です。だからこそ、「何を一番大切にするか」を整理しておくことがポイントです。
【家庭で話し合っておきたい優先項目】
- 通学時間は何分以内が理想か?
- 自由な校風 vs 規律ある校風、どちらが合いそうか?
- 大学進学重視 or 自分のやりたいことを優先?
- 部活を続けたい or 勉強に集中したい?
- 公立と私立、学費面での制約はあるか?
これらを親子で紙に書き出して優先順位をつけることで、説明会や見学のときにもブレずに判断できるようになります。

経済面や通学距離など、保護者として考えなければならない点も多いと思いますが、だからこそ、お子様の思いや希望をよく話し合ったうえで、一緒に最適な進路を考えたいですね。
高校選びは「行動した分だけ、納得できる」
いかがでしたか?今回は『高校見学はいつから?何を見る?親子で後悔しないためのチェックポイント』をご紹介しました。
高校選びは、一度きりの大きな選択です。でも、事前に動いて見ておけば、不安は大きく減り、「この学校で頑張りたい!」という気持ちも育ちます。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。